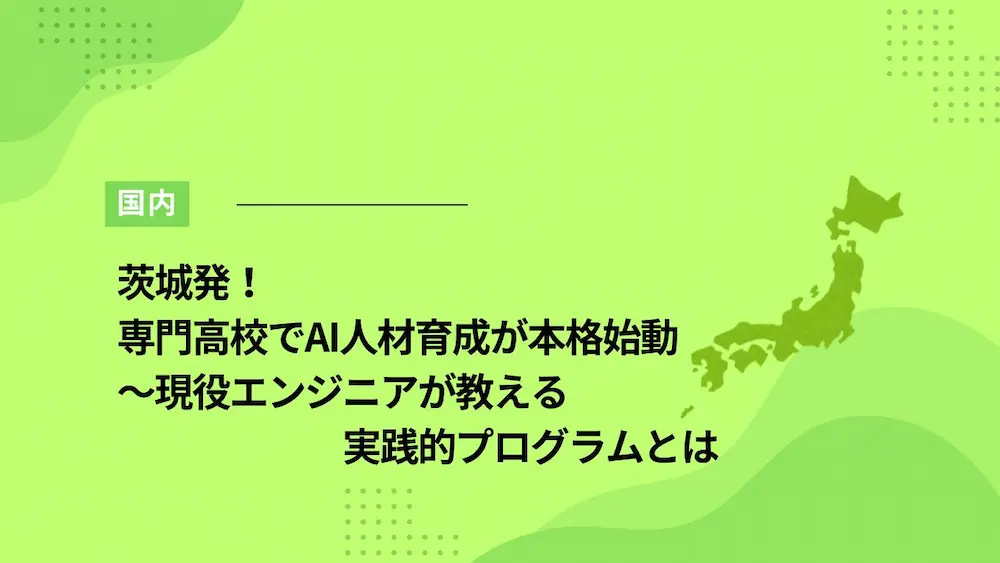
茨城県の2つの専門高校で、画期的なAI教育プログラムが始まりました。
現役AIエンジニアと教育の専門家がタッグを組み、高校生が大規模言語モデルを学び、オリジナルの生成AIチャットボット開発に挑戦します。
探究型学習を取り入れたこの先進的な取り組みは、理論と実践を融合させた新しい学びのモデルとして、全国の学校現場に示唆を与えるか…AI時代を担う人材育成の事例を見てみましょう。
記事の要約
株式会社サードウェーブ(東京都千代田区)は、特定非営利活動法人NASEF JAPAN(東京都千代田区)と共に茨城県教育委員会の「プログラミング・エキスパート育成事業」を受託し、茨城県立IT未来高等学校 および茨城県立つくばサイエンス高等学校でAI講座を開始した。
同社の現役AIエンジニア集団の技術知見と、全国で高校生向けデジタル講座を展開してきたNASEF JAPANの教育ノウハウを融合させた実践的カリキュラムである。
生徒は大規模言語モデル(LLM)の仕組みを学び、チームでオリジナルの生成AIチャットボット開発に挑戦する。
探究型学習を取り入れ、生徒が主体的に課題を発見し解決を目指す構成だ。
AI開発現場の最新技術と教育的配慮を組み合わせることで、理論と実践の両面から未来のAI人材育成を支援する先進的な取り組みである。
茨城県教育委員会は、この高度なAI教育が生徒の可能性を広げ、時代のニーズに応える人材育成につながることを期待している。
(出典元:2025年10月15日 ドスパラのプレスリリース・お知らせより)
今後の学校教育への展開と可能性は?
この取り組みは、専門高校だけでなく普通科高校への展開も期待されます。
AI技術の理解は、理系分野に限らず文系科目や総合的な探究の時間にも応用可能です。
例えば、歴史や文学の学習支援AIチャットボット開発を通じて、教科横断的な学びが実現できます。
また、現役エンジニアと教育専門家が協働するモデルは、学校と産業界の新たな連携形態として注目されるでしょう。
生徒は最新技術に触れながら、実社会で求められるスキルを早期から習得でき、探究型学習との組み合わせにより、問題発見力や協働的思考力も育成されます。
将来的には、この実践事例が全国の学校に広がり、地域の企業や大学と連携したAI教育ネットワークの構築につながる可能性があります。
さらに、高校生がAI開発の基礎を学ぶことで、大学や専門学校での学びがより深まり、日本のAI人材不足の解消にも貢献するでしょう。
生徒一人ひとりが技術の担い手として成長する教育モデルの確立が期待されます。
情報元はこちらからご覧ください。
https://cts.dospara.co.jp/5press/share_info.php?id=3359
