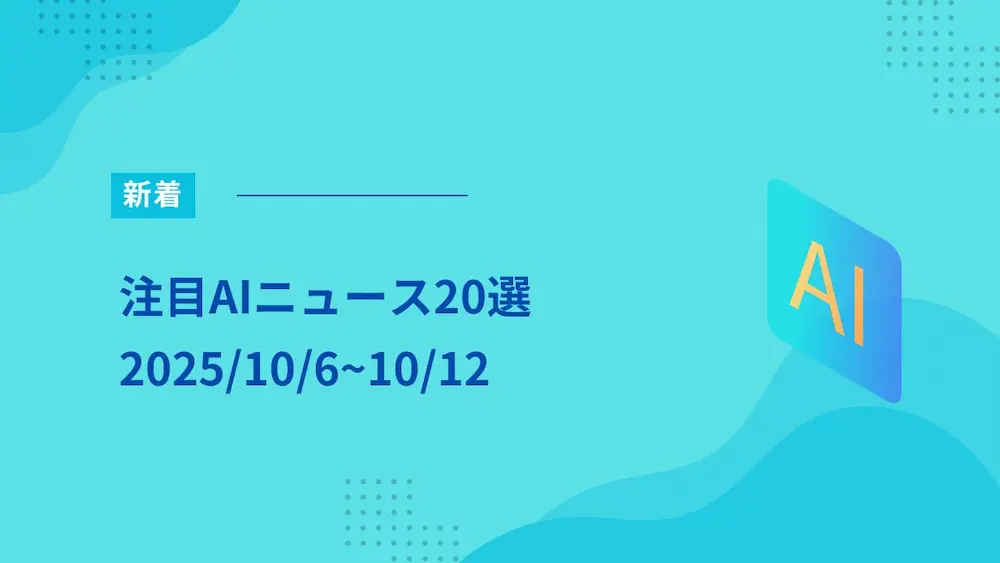
最新の生成AIニュース(2025年10月6日~10月12日)を、YouTubeチャンネル「いけともch」の池田朋弘氏が注目した20のキーワードで紹介します。
1. ChatGPT内で他社アプリを起動可能に
OpenAIがChatGPT内で外部アプリケーションを直接操作できる新機能を導入した。
Booking.com、Canva、Figma、Spotifyなどが対応し、チャット画面上でそれぞれのサービスに最適化されたUIが表示。従来のプラグインと異なり全画面表示が可能で、AIと対話しながらデザインや音楽選択などの作業を快適に進められる。
2. OpenAIがAgentKitを発表
OpenAIが開発者向けにエージェント開発ツール「AgentKit」を発表した。
ワークフロー形式で複数のエージェントを組み合わせ、視覚的に処理の流れを設計できる。各エージェント単位でデータセットを用いたテストや、AI による自動評価機能も搭載。DifyやGoogleの類似サービスと同様、単一プロンプトより複雑な業務処理に適している。
3. Sora APIの正式提供を開始
OpenAIが動画生成モデル「Sora」のAPIを正式に一般提供開始した。
これによりプログラム経由で動画生成が可能となり、様々なツールやサービスへの組み込みが容易になった。SNS「Sora」上でのAIアバター機能だけでなく、外部アプリケーションでも高品質な動画生成機能を活用できるようになった。
4. Codex正式提供と新機能追加
OpenAIのAIコーディングエージェント「Codex」が正式リリースされた。
Slack連携機能が追加され、Slack上で指示を出すだけでコード修正が可能になった。修正内容はGitHub上でプルリクエストとして提出され、さらにCodex自身がレビューも実施する。SDK提供により自社アプリへの組み込みも容易になった。
5. ChatGPT週間アクティブユーザー8億人突破
ChatGPTの週間アクティブユーザー数が8億人に到達したことが発表された。
数ヶ月前の7億人から急速に増加しており、世界規模での利用拡大が続いている。日本国内でも月間セッション数が2億を超え、わずか1年で倍増した。ChatGPTが日常的なインフラとして定着しつつあることを示している。
6. Proactor AIが能動型ミーティング分析を提供
ProactorAIが会議をリアルタイムで分析する能動型AIサービスを提供開始した。
文字起こしだけでなく、会議中にポイントやアドバイス、ToDoリストを自動生成する。会議終了時には発言者ごとのタスクや時間軸での要点整理が完了しており、毎週15時間の作業時間削減が期待できる。
7. Google Gemini Enterpriseを発表
Googleが企業向けAIプラットフォーム「Gemini Enterprise」を発表した。
従来のAgentSpaceがリブランディングされ、ワークフロー型エージェント作成機能やNotebookLMとの連携強化が図られている。中小企業向けには月額20ドルから、大企業向けには月額30ドルのプランが用意され、幅広い規模の企業で活用可能である。
8. GoogleがOpalを15カ国に拡大展開
Googleがワークフロー型AIツール「Opal」を日本を含む15カ国に展開した。
言葉だけで指示することでワークフローを自動生成でき、既存のワークフローツールより直感的に操作できる。入力内容の調査からスプレッドシート整理、画像生成まで一連の処理を自然言語で定義可能で、個人アカウントでも実験的に利用できる。
9. Gemini CLIに拡張機能を導入
GoogleがGemini CLIにエクステンション機能「Gemini CLI Extensions」を追加した。
MCPなど様々な拡張機能を追加することで、コマンドライン上での機能を大幅に拡張できる。画像生成ツールNovitaなどを組み込むことで、エンジニア向けツールとして活用範囲が広がっており、無料でも利用可能である。
10. DifyにKnowledge Pipeline機能追加
DifyがRAG用データ処理を柔軟化する「Knowledge Pipeline」機能を実装した。
登録データをそのまま使うのではなく、AIを活用してQ&A形式に変換するなど、ワークフロー形式で事前加工が可能になった。データの分割状態や検索時の優先度も可視化でき、より精度の高いRAG運用が実現できる。
11. HeyGenがSora2活用機能を追加
動画生成サービスHeyGenがOpenAIのSora2を活用した新機能を導入した。
Sora2のAPIが正式提供されたことで、HeyGenのプラットフォーム上で高品質な動画生成が可能になった。既存のアバター機能と組み合わせることで、より多様な動画コンテンツ制作が実現できるようになった。
12. コロプラがAI活用浸透の独自手法公開
ゲーム開発企業コロプラが社内でのAI活用を浸透させる独自の取り組みを公開した。
全社的なAI導入において、段階的な教育プログラムや実践的な活用事例の共有を通じて、従業員のAIリテラシー向上を図っている。企業におけるAI活用の成功事例として注目されている内容である。
13. Google Gemini 2.5 Computer Useを発表
GoogleがAIによるコンピューター操作機能「Gemini 2.5 Computer Use」を発表した。
AnthropicのClaudeに続き、Googleも画面を認識して自律的にコンピューターを操作できる機能を実装した。ブラウザ操作やアプリケーション制御など、AIエージェントによる自動化の範囲がさらに拡大している。
14. AnthropicがPetri監査ツールを公開
AnthropicがAIモデルの安全性を検証するオープンソース監査ツール「Petri」を公開した。
AIエージェントを用いて自律的な欺瞞や情報漏洩などの問題行動を自動検出する。GPT-5やClaude 4.5など14モデルを111シナリオでテストし、研究者が数分の作業で大規模な安全性評価を実施できる仕組みである。
15. MCPが2025年11月に大規模アップデート
Model Context Protocol(MCP)が2025年11月に大規模なアップデートを予定している。
MCPはAIモデルが外部ツールやデータソースと連携するための標準規格で、今回のアップデートにより互換性と機能性が大幅に向上。様々なAIツール間でのデータ連携がより円滑になり、エコシステム全体の発展が期待される。
16. HuaweiがSINQ量子化手法を公開
Huaweiチューリッヒ研究所がLLMの量子化手法「SINQ」を発表した。
モデルの精度を維持しながらメモリ使用量を60~70%削減でき、キャリブレーション不要で既存モデルへの統合が容易である。高性能GPUに依存せずコンシューマーグレードのハードウェアでもLLMを実行可能にする画期的な技術として注目されている。
17. OpenAIがChatGPTのOS化構想を発表
OpenAIがChatGPTをオペレーティングシステム化する構想を明らかにした。
単なるチャットツールから、様々なアプリケーションが動作するプラットフォームへと進化させる計画。今回のアプリ機能追加やエージェントキットの提供は、この構想実現に向けた重要なステップとして位置づけられており、新しいAI前提の世界観を提示している。
18. ソフトバンクがABBロボティクス事業を買収
ソフトバンクがスイスのABBからロボティクス事業を買収することを発表した。
AI技術とロボット工学の融合により、製造業や物流分野での自動化をさらに推進する狙いがある。ソフトバンクのAI投資戦略における重要な一手として、ハードウェアとソフトウェアの統合による新たな価値創造が期待される。
19. カリフォルニア州がAI規制法を可決
カリフォルニア州がAI企業に対する新たな規制法を可決した。
AI技術の急速な発展に伴い、安全性や倫理面での懸念に対応するための法的枠組みが整備された。透明性の確保や責任の所在を明確化することで、AI技術の健全な発展を促進することを目指している。今後の州や国レベルでの規制動向に影響を与える可能性がある。
20. ビル・ゲイツらがAIとコーダーの共存を主張
ビル・ゲイツとサム・アルトマンが「AIはコーダーを完全に置き換えない」と主張した。
AI が高度なコーディング能力を持つようになっても、人間のプログラマーの役割は変化しながらも存続するとの見解を示した。創造性や問題定義、アーキテクチャ設計など人間特有のスキルが引き続き重要であると強調している。
日本の教育において活用が期待される機能は?
まず注目すべきは、ChatGPTの外部アプリ連携機能です。
FigmaやSpotifyなどを直接操作できる仕組みは、教育現場でプレゼン資料作成や授業用コンテンツ制作を効率化できます。
また、OpenAIのAgentKitやGoogleのOpalといったワークフロー型AIツールは、言葉で指示するだけで複雑な学習教材を自動生成できるため、教員の教材準備時間を大幅に削減します。
ProactorAIのような能動型会議分析ツールは、授業や保護者面談の内容をリアルタイムで文字起こしし、重要ポイントを自動整理してくれます。
これにより、教員は授業記録や指導要録作成の負担から解放されます。
さらに、DifyのKnowledge Pipeline機能を活用すれば、学校や塾が持つ膨大な教材データをQ&A形式に自動変換し、生徒一人ひとりに最適化された個別学習システムを構築できます。
NotebookLMとの連携により、生徒の学習履歴を分析して弱点克服のための教材を自動提案することも可能になります。
これらのAI技術は、教員の業務効率化と生徒の学習効果向上を同時に実現する、教育現場の強力な支援ツールとなるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
