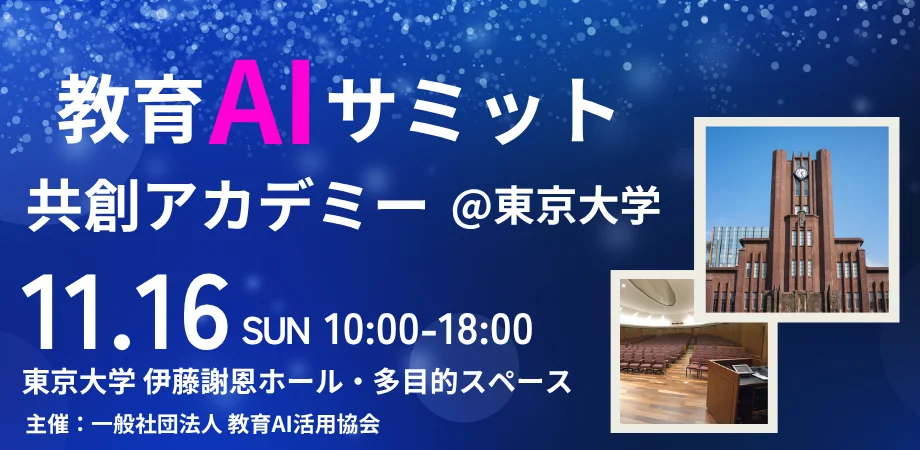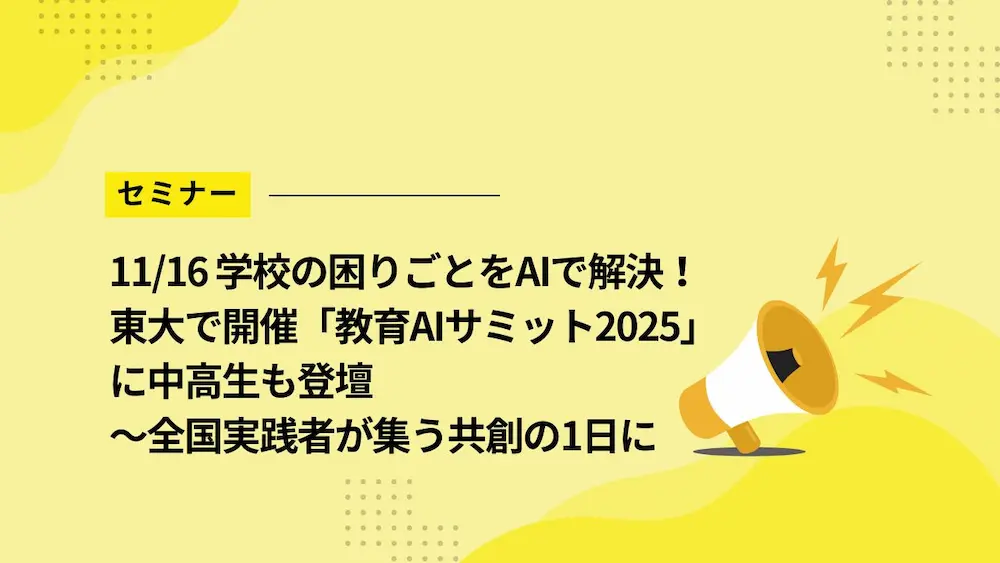
学習意欲の低下、個別最適化の課題、教員の業務負担…。
こうした学校現場の悩みにAIはどう応えるのでしょうか。
今年11月16日、東京大学で開催される「教育AIサミット2025」では、全国から集まった教員による実践コンテストや、中高生と教員が一緒に学校課題を解決するアプリ開発ワークショップが行われます。
慶應義塾大学名誉教授らが探究学習とAIの融合を議論し、オルタナティブ教育の未来も展望します。
AI初心者も歓迎、参加無料のこのイベントは、教育の新しい形を「共創」する貴重な機会となるはずです。
記事の要約
一般社団法人教育AI活用協会(東京都港区)は、2025年11月16日に東京大学で「教育AIサミット ~共創アカデミー」を開催する。
本サミットは教育関係者、研究者、企業が立場を超えて新たな教育の形を共創する場で、参加費は無料。
主要プログラムとして、AI時代の学習意欲減退への処方箋を探るトークセッション、小学館コラボによる「学校現場のAI活用実践コンテスト2025」、多様な学びとオルタナティブ教育の未来を議論するセッションが予定されている。
特筆すべきは、中高生から教員、企業関係者まで世代を超えたチームが学校の課題を解決するAIアプリをその場で作成する「共創アプリワークショップ」。
ChatGPTやVercel v0などのツールを使用し、AI初心者も参加可能な体験型企画となっている。
また、高校生や大学生が企画運営の中心を担う点も注目される。
(出典元:2025年11月5日 PR TIMES・一般社団法人教育AI活用協会より)
今後の学校教育に生かせる内容や可能性は?
このサミットは、日本の学校教育に三つの重要な示唆を与えています。
第一に、AI活用における世代間・立場間の協働モデルです。
中高生と教員、企業関係者が対等にチームを組んでアプリ開発を行う体験型ワークショップは、従来の教える-教えられる関係を超えた学びの形を示しています。
第二に、探究学習とAIの融合による学習意欲の回復可能性です。
慶應義塾大学名誉教授らが登壇するセッションでは、AIを探究ナビゲーターとして活用する具体的アプローチが共有されます。
第三に、実践事例の可視化と横展開です。
全国から集まったAI活用実践をコンテスト形式で共有することで、各学校が参考にできる具体的モデルが提示されます。
将来的には、AIツールを日常的に活用しながら、生徒が主体的に課題を発見し解決する探究型授業が全国の学校に広がる可能性があります。
特に注目すべきは、生徒自身がAIアプリ開発者となり、学校の困りごとを技術で解決する経験が、将来のイノベーション人材育成につながる点です。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000023.000161501.html