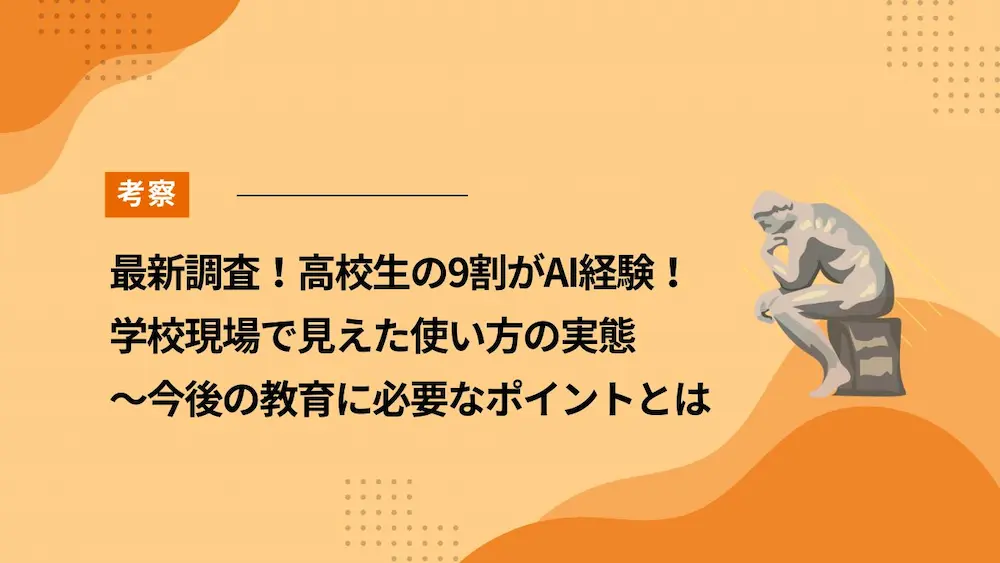
生成AI時代の学校教育現場に、新たな兆しが見えたかもしれません。
最新調査によると、高校生の92.5%が生成AIを経験し、驚くべきことに6割以上が「情報をそのまま使わず、自分なりに解釈して活用」していることが判明しました。
探究学習での情報収集ツールとして定着する一方で、若者たちは「人とのつながり」や「創造力」といった人間らしさを何より大切にしています。
AI時代だからこそ問われる教育とは何か…学校現場で起きている変化と、これからの教育に必要な視点を探ってみましょう。
【記事の要約】
株式会社リクルート(東京都千代田区)が実施した高校生688人を対象とした生成AI利用調査によると、現在も生成AIを使用している高校生は83.1%、利用経験者は92.5%に達した。
学校・学習での主要な使用シーンは「総合的な探究の時間などの調べ学習」が1位となり、「課題の自己採点や添削」「生成AIを活用した教材やテスト問題の活用」が続いた。
注目すべきは、生成AIの回答を「自分なりの解釈で情報を整えて使う」高校生が60.8%を占め、「そのまま使う」は13.7%にとどまったことである。
将来的には「効率的な情報収集や整理」での活用を期待する声が最も多く、生成AIを使えること自体を強みとする考え方は少数派であった。
高校生は生成AIを協力者として捉える一方で、「人とのつながりやコミュニケーション」や「自分で考える力や創造力」といった人間らしさを重視している。
(出典元:2025年9月16日 PR TIMES・株式会社リクルートより)
今後の学校教育への活用と可能性は?
この調査結果は、今後の学校教育における生成AI活用の方向性を示す指針となりそうです。
まず注目すべきは、高校生の9割以上が生成AIを経験し、適切な距離感を保ちながら活用している点です。
文科省のガイドラインに沿った教育の成果が表れており、情報リテラシー教育の重要性が改めて確認されました。
学校教育では、探究学習での活用が最も多いことから、課題発見・情報収集・分析のプロセスにおいて生成AIを効果的に組み込む教育手法の開発が求められます。
特に「自分なりの解釈で情報を整えて使う」という姿勢は、批判的思考力の育成につながる重要な要素です。
教育現場では、生成AIの回答を鵜呑みにせず、検証・比較・再考する習慣を身につけさせる指導が必要でしょう。
将来的には、生成AIが「情報収集や整理の効率化」「多角的視点の獲得」「表現力向上」の支援ツールとして定着することが予想されます。
しかし、高校生が「人とのつながり」や「創造力」を重視していることから、AI時代だからこそ人間固有の能力を伸ばす教育の必要性が浮き彫りになっています。
学校教育は、技術活用スキルと人間性の両立を図り、生成AIと協働しながらも主体性を保てる人材育成を目指すべきといえるでしょう。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003089.000011414.html
