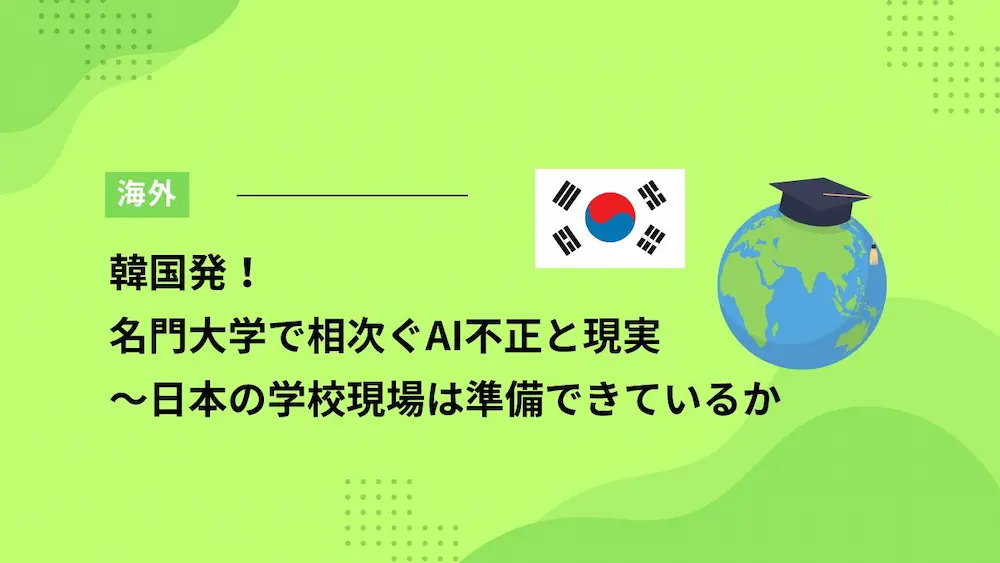
韓国の延世大学、高麗大学、ソウル大学といった名門校で、チャットGPTを利用した大規模な不正行為が発覚し、教育界に衝撃が走っています。
受講生600人規模の講義で多数の学生がAIを悪用し、SNSアプリ・カカオトークで答案を共有する事態まで起きました。
驚くべきは、全国131校の大学のうちAIガイドラインを整備したのはわずか22.9%という現実です。
2022年末のチャットGPT登場から約3年が経過した今も、多くの教育機関が無防備なまま放置されているといってもいい状況…この問題は対岸の火事ではありません。
日本の小中高校や大学でも、AIリテラシー教育の体系化と明確な使用指針の策定が急務となっています。
記事の要約
韓国の名門大学で人工知能を活用した大規模な不正行為が相次いで発覚し、教育界に衝撃を与えている。
延世大学校(ソウル市)では600人規模の「自然言語処理とチャットGPT」講義の中間試験で多数の学生がAIによる不正行為を働き、高麗大学やソウル大学でも同様の事例が確認された。
非対面試験では動画提出で監視したものの、学生らはカメラの死角を利用して不正を行った。
最も深刻な問題は、教育機関側の対応の遅れである。2022年末のチャットGPT公開以降、こうした事態は予測可能だったにもかかわらず、全国131校の大学のうちAIガイドラインを採択したのはわずか30校(22.9%)に過ぎない。
調査では91.7%の学生がAIを課題に利用している一方、71.1%の大学がガイドライン未整備という実態も明らかになった。
政府レベルでの積極的な指針提示と、AI時代に適した講義・評価方法の抜本的な見直しが急務となっている。
(出典元:2025年11月10日、同13日 ハンギョレ新聞より)
今後の日本の学校教育への示唆は?
この事例は日本の学校教育にとって重要な警鐘となるでしょう。
まず、AIツールの普及を前提とした教育システムの再構築が不可欠です。
従来の知識暗記型評価からの脱却を図り、AIを適切に活用しながら批判的思考力や創造性を育む評価方法へと転換する必要があります。
具体的には、小中高校の段階から「AIリテラシー教育」を体系的に導入し、AIの適切な使用範囲と倫理的な活用方法を明確に指導することが求められます。
また、対面でのディスカッションやプレゼンテーション、実践的なプロジェクト学習など、AIでは代替できない学習活動の比重を高めることも効果的でしょう。
将来的には、AIを「禁止する対象」ではなく「共に学ぶパートナー」として位置づけ、生徒がAIの長所と限界を理解しながら、人間ならではの判断力や創造力を伸ばす教育モデルの確立が期待されます。
文部科学省や教育委員会レベルでの統一的なガイドライン策定と、教員研修の充実が急務となるはずです。
情報元はこちらからご覧ください。
https://japan.hani.co.kr/arti/politics/54688.html
https://japan.hani.co.kr/arti/opinion/54717.html
