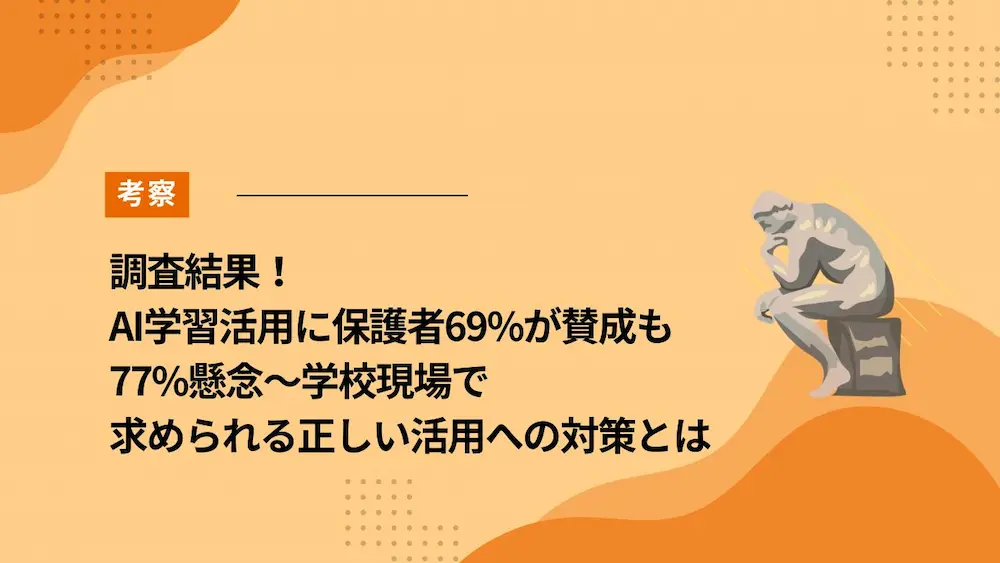
高校生の学習における生成AI活用が急速に進む中、保護者への意識調査で興味深い結果が明らかになりました。
活用に賛成する保護者が69%に上る一方で、77%が「考える力が育たない」などの懸念を抱いています。
特に日常的に生成AIを使う保護者ほど、その価値とリスクを同時に体感している実態が浮き彫りになりました。
学校現場では今、この「便利さとリスクの両立」をどう図るかが問われています。
フィルタリング機能や考える力を促す仕組みなど、具体的な対策への期待が高まる中、教育現場はどう対応すべきでしょうか。
記事の要約
Hanji株式会社(東京都品川区)による2025年9月の調査で、高校生の保護者222人を対象に生成AIの学習活用について調べた結果が発表された。
保護者の69%が生成AIを日常的またはたまに利用し、子どもも同様に69%が使用している。
子どもの学習での生成AI活用については69%が賛成で、特に日常的に使う保護者では91%が賛成。
しかし全体の77%が懸念を持ち、活用に賛成する保護者でも86%が何らかの懸念を抱いている。
主な懸念は「考える力や問題解決力が育たない」(63%)、「困難な課題に粘り強く取り組む姿勢が育たない」(54%)といった学習姿勢への影響である。
対策としてはフィルタリング機能(52.6%)や、自分で考えることを促す仕組み(50.3%)が求められている。
(出典元:2025年10月9日 PR TMES・Hanji株式会社、同10日 こどもとITより)
今後の認識と教育現場への示唆は?
この調査は、生成AIが高校生の学習環境にすでに深く浸透している現実を示しています。
まず、保護者自身が生成AIを活用するほど、その教育的価値とリスクを同時に認識している点は重要です。
学校教育においては、生成AIの利用を禁止するのではなく、「正しい活用」を前提とした教育方針の転換が求められます。
文部科学省が2024年12月に示した『初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン』を踏まえ、各学校が具体的な運用ルールを策定する段階に入っています。
◆思考力育成との両立戦略
最大の懸念である「考える力の低下」に対しては、生成AIを思考のプロセスを可視化するツールとして活用する方法が有効です。
例えば、AIの回答をそのまま使うのではなく、その回答を批判的に検証したり、複数の回答を比較して最適解を導き出したりする学習活動を設計することができます。
また、調査で求められている「自分で考えることを促す仕組み」を授業設計に組み込み、AIを補助的な学習パートナーとして位置づけることが重要です。
◆協働体制の構築
保護者・学校・事業者の三者協働が今後の鍵となります。
学校では教員向けの実践的な研修を実施し、短時間で参加しやすい形式で生成AIリテラシーを向上させることが必要です。
家庭では保護者と子どもが一緒に生成AIの適切な使い方を学び、学校と家庭で一貫した指導方針を共有することで教育効果が高まります。
事業者側には、フィルタリング機能やモニタリング機能の充実、考えるプロセスを促進する設計の改善が期待されています。
◆段階的実践の重要性
調査の考察にあるように、利用の可否を二者択一にせず、目的や場面を限定した試行と振り返りを積み重ねることが現実的なアプローチです。
各学校が自校の実態に合わせて、教科や学習場面ごとに活用範囲を設定し、生徒の反応や学習成果を検証しながら段階的に拡大していく方法が推奨されます。
このプロセスを通じて、生成AIの便利さとリスクのバランスを取りながら、次世代に必要なAI時代の学習スキルを育成することが可能になるでしょう。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000167901.html
https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/2054332.html
