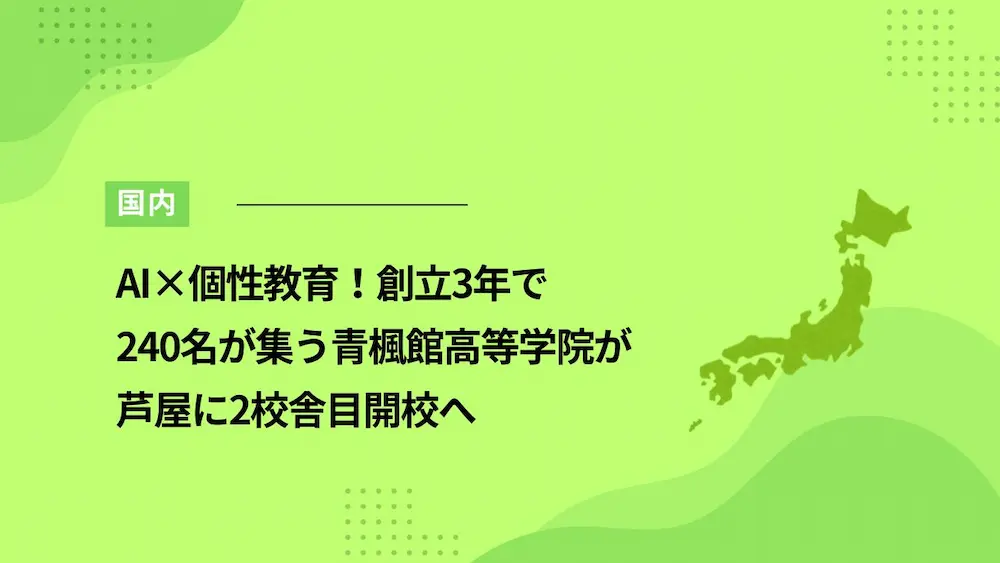
不登校生徒の増加やAI時代に必要な学びの変化に直面する学校教育現場において、新たな教育モデルが注目を集めています。
2023年創立からわずか3年で240名超の生徒を抱える通信制サポート校「青楓館高等学院」が、2026年4月に兵庫県芦屋市へ2校舎目を開校します。
従来の学力偏重型から「個性教育」へと転換した同校の実践は、公教育が今後取り入れるべき多くのヒントを提供しています。
記事の要約
通信制サポート校の青楓館高等学院(兵庫県明石市)は、2026年4月に兵庫県芦屋市に2校舎目となる芦屋校を開校する。
2023年の創立から3年で240名超の生徒を抱える同校は、学力偏重ではなく「個性教育」を実践する次世代型の教育機関である。
創設者の岡内大晟氏は、学校と社会のギャップ、不登校の増加、AI時代に求められる教育という課題に向き合い、企業の商品開発や行政との町おこしなど独自カリキュラムを通じて、学びの多様性と社会で生き抜く力の両立を支援している。
同校はOECDプロジェクトへの参画、AI先端モデル校認定、海外75大学との提携、週1回の1on1面談、PBL型学習、非認知スキルを可視化する「バッジ制度」など先進的な取り組みで国内外から注目を集めている。
今後は全国展開、国際ネットワークの強化、地域共創、AIと個性教育の融合を柱に、2年後に1,000名規模を目指す。
(出典元:2025年10月6日 PR TIMES・株式会社青楓館より)
日本の学校教育への影響と可能性は?
青楓館の実践は、従来の学力中心主義から脱却し、個性と社会接続を重視した教育モデルとして、今後の学校教育に多くの示唆を与えます。
週1回の1on1面談による個別支援や、企業・自治体と連携したPBL型学習は、生徒一人ひとりの強みを発見し伸ばす仕組みとして、通常の学校でも応用可能です。
特に、非認知スキルを可視化する「バッジ制度」は、テストの点数だけでは測れない成長を評価する新しい方法として注目されます。
また、AI先端モデル校としての取り組みや海外75大学との提携は、グローバル化とテクノロジー活用が進む時代に、生徒の選択肢を広げる実践例です。
不登校生徒の増加という社会課題に対しても、画一的でない学びの場を提供することで、多様な生徒が自分らしく成長できる環境づくりのモデルケースとなっています。
このような個性教育と社会実践を融合させたアプローチは、公教育においても参考にすべき重要な視点といえるでしょう。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000106384.html
