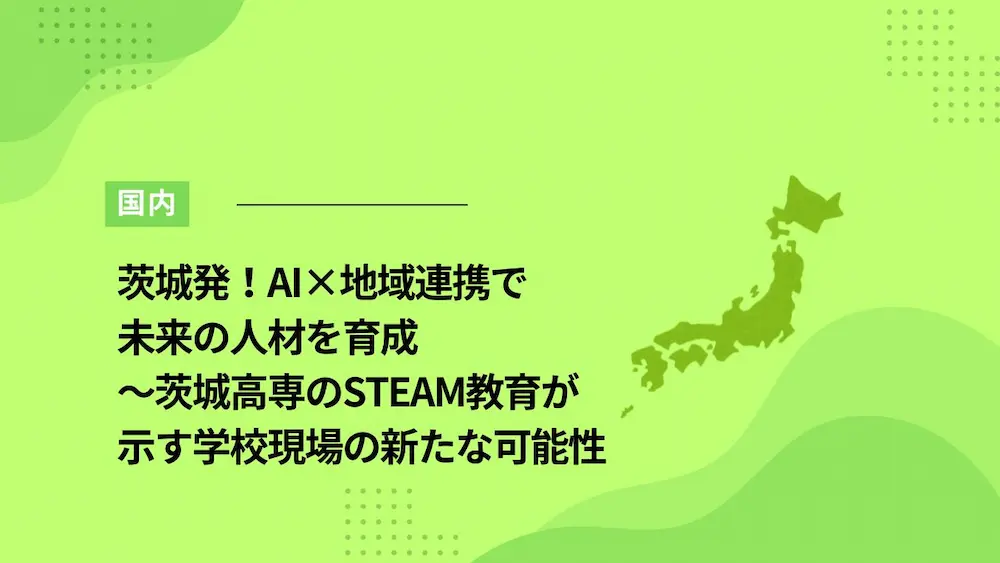
教育現場における生成AIの活用が注目を集める中、茨城高専が実践した「KOSEN×勝田中等サマースクール」は、従来の教育手法を大きく変える可能性を秘めています。
この取り組みでは、中学生21名が高専生の支援を受けながら生成AIをパートナーとして活用し、地域課題の解決に挑戦しました。
注目すべきは、AIに依存するのではなく、まず人間中心のアイデア創出から始め、その後AIで具体化するという段階的アプローチです。
参加した中学生の90%以上が「新しい学びを得られた」と回答し、教育効果の高さが実証されていますが、その内容をもう少し見てみましょう。
【記事の要約】
茨城工業高等専門学校(茨城県ひたちなか市)は、STEAM教育の一環として茨城県立勝田中等教育学校で生成AIを活用した出前授業「KOSEN×勝田中等サマースクール」を実施した。
本授業では、中学生21名が高専生の技術支援を受けながら、生成AIを活用して地域活性化のアイデアを創出・発表するプログラムに取り組んだ。
茨城高専は生成AIを「作業効率化の道具」ではなく「人間の思考力を育むパートナー」として位置づけている。
生成AI活用型PBL(AI-PBL)では、まず人間中心でKJ法を用いたアイデア創出を行い、その後に生成AIを活用して具体的な提案レベルに落とし込む手法を採用した。
廃校を「昼はコンセプトカフェ、夜はお化け屋敷」として活用するといった独創的なアイデアが発表され、参加した中学生の90%以上が「新しい学びが得られた」と回答した。
(出典元:2025年9月26日 PR TIMES・独立行政法人国立高等専門学校機構より)
今後の学校教育への活用と可能性は?
この取り組みは、従来の詰め込み型教育から探究型学習への転換を促す画期的な教育モデルです。
生成AIを思考のパートナーとして位置づけることで、生徒たちは自分自身の創造性や批判的思考力を育みながら、テクノロジーとの適切な関係性を学べます。
特に注目すべきは、人間中心のアイデア創出から始まり、その後AIを活用して具体化するという段階的なアプローチです。
これにより生徒たちはAIに依存することなく、自らの思考力を基盤とした問題解決能力を身につけられます。
また、高専生がティーチングアシスタントとして参加することで、異年齢間の学び合いも実現されています。
将来的には、この教育手法を中学・高校の各教科に応用することで、より実践的で社会に直結した学習が可能になります。
地域の課題解決をテーマとしたプロジェクト学習は、生徒たちの社会参画意識を高め、次世代のイノベーション人材育成に大きく貢献するでしょう。
情報元はこちらをご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000524.000075419.html
