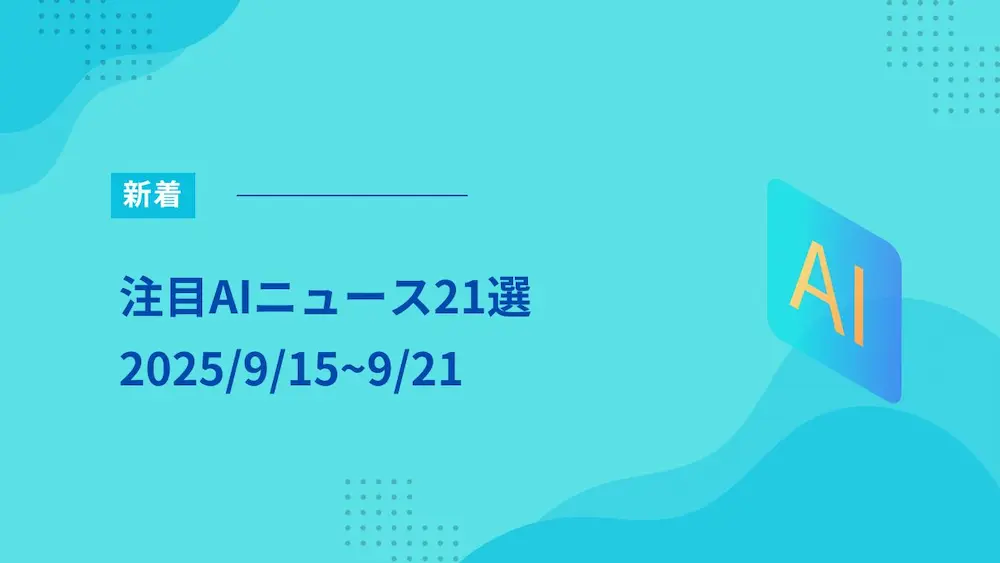
最新の生成AIニュース(2025年9月15日~9月21日)を、YouTubeチャンネル「いけともch」の池田朋弘氏が注目した21のキーワードで紹介します。
1. Google NotebookLMが学習支援機能を拡充
NotebookLMにフラッシュカードとクイズ機能が新たに追加された。
フラッシュカードは単語や概念の暗記に活用でき、クリックで答えを確認できる仕組みである。クイズ機能では4択形式のテストが生成され、学習内容の理解度をチェックできる。今後はラーニングガイド機能も追加予定で、質問形式での段階的学習が可能になる見込みだ。
2. GoogleがGeminiのGemsを共有可能にアップデート
これまで個人のみで利用可能だったGeminiのGems機能が、他のユーザーとの共有に対応した。
共有時には編集権限と閲覧権限を選択でき、GoogleWorkspaceでも個人アカウントでも利用できる。編集権限で共有した場合、共有相手による変更が元の作成者にも反映されるため、権限設定には注意が必要。
3. ChatGPTコネクタに「Developer mode」追加~書き込み対応が拡大
ChatGPTのコネクター機能にデベロッパーモードが追加され、外部サービスへの書き込み操作が可能になった。
これまでは読み取りのみだったが、NotionやStripeなどのサービスに直接データを書き込める。例えばNotionの情報を分析し、結果を新しいページとして自動作成することが可能だ。ただし書き込み権限にはリスクが伴うため、慎重な利用が求められる。
4. ChatGPTのThinkingに「思考の長さ」を指定可能に
ChatGPTのThinking機能で思考時間の調整が可能になった。
軽め、標準、じっくり、深いの4段階から選択でき、プロプランでは全てのレベルが利用できる。簡単な質問では各レベル間の差は小さく、標準モードから始めて回答が不十分な場合にじっくりモードを試すのが推奨される。難しい問題や詳細な比較が必要な場合に特に有効である。
5. Microsoft TeamsにAI Agent(Copilot Agents)が導入
Microsoft TeamsにCopilot Agentsが本格導入され、チャンネル専用エージェントの作成が可能になった。
各チャンネルの文脈を理解したエージェントが質問に回答し、スケジュール管理やToDo管理も支援する。オンライン会議では、AIファシリテーターがアジェンダ管理や時間管理を行い、会議後のタスク整理も自動化される。実用的な機能として期待されている。
6. AIプレゼンテーションツールGamma3.0登場
Gamma3.0でGammaエージェントが導入され、Web検索機能とAPI連携が追加された。
エージェントにスライド改善を依頼すると、Web検索で情報を収集し、内容を充実させたスライドを自動生成する。画像データからスライド作成も可能で、表形式のデータも適切なレイアウトで変換される。Zapier連携により、データ入力からスライド生成までの完全自動化も実現している。
7. Notion 3.0でAIエージェントによる「動く Notion」
Notion 3.0でAIエージェント機能が追加され、最大20分間の作業で複数ページや内容を分析・整理できるようになった。
直近100件のニュース分析やトレンド整理など、データベース内の情報を自動でまとめる機能を持つ。会議メモからの提案書作成やオンボーディングプラン作成も可能で、Slackなど外部ツールからの情報収集にも対応している。
8. OpenAIが「Codex」に新モデル「GPT-5-Codex」を導入
OpenAIがコーディングエージェント「Codex」にGPT-5-Codexという新モデルを導入した。
このモデルはゼロからのプロジェクト構築、大規模なリファクタリング、コードレビューなど実務レベルのタスクに最適化されている。動的に思考時間を調整し、簡単なタスクは高速処理、複雑なタスクは最大8分間作業を継続する。カーソルやVS Codeでも利用でき、コードの精度向上に寄与している。
9. ChromeにGemini統合~AI搭載ブラウザの新時代へ
GoogleがChromeブラウザにGeminiを統合する機能をアメリカで開始した。
右上のGeminiボタンから文書内容の要約、複数タブの比較、直接質問が可能になる。アドレスバーに入力するとAIモードに切り替わり、Geminiのような回答が得られる。今後は段階的にエージェント機能が追加され、買い物や予約といった実用的なタスクにも対応予定。
10. YouTubeが生成AI活用の新クリエイティブ機能を発表
YouTubeがVEO3を使った動画生成、静止画からの動画作成、複数クリップの自動ショート動画編集機能を発表した。
VEO3により高品質な企画動画の制作が可能になり、静止画にモーションを加えた動画作成も簡単になった。既存の動画から30秒程度のショート動画を自動生成する機能や、映像に合わせた音楽自動生成機能も追加され、クリエイターの作業効率化が大幅に進む。
11. Amazonが出品者を支援するエージェント「Seller Assistant」発表
AmazonがセラーアシスタントというAIエージェントをリリースし、独立セラーの販売支援を強化した。
在庫分析、価格調整、アカウント管理、商品違反チェックなどを自動化する。従来のプロジェクトアメリアはQ&A形式だったが、セラーアシスタントは積極的に提案を行う。Amazon25年間の販売データとノウハウを活用し、優秀なコンサルタント並みの支援を提供する。
12. Amazonが広告制作を支援する新AIツール提供開始
Amazonがクリエイティブスタジオ機能を通じて広告制作支援ツールを提供開始した。
商品を入力するとコンセプトを3つ提案し、選択したコンセプトからストーリーボード、音楽、音声を自動生成する。最終的に映像や画像を作成してAmazon上で出稿できる仕組み。従来は予算と優秀なクリエイターが必要だったが、この機能により無料で高品質な広告制作が可能になった。
13. Google HomeアプリがGemini統合でリニューアル
GoogleHomeアプリにGeminiが統合され、スマートスピーカーとの連携が強化された。
Googleアシスタントに代わってGeminiが音声対話を担当し、ホームデバイスの設定や操作を音声で実行できる。アプリ内でもGeminiに相談してスマートホームの設定を簡単に行える。今後スマートスピーカーのAI機能がより高度になり、音声による家電操作の利便性が大幅に向上する見込み。
14. ZoomがAI Companion 3.0を発表
ZoomがAI Companion 3.0という新機能を発表し、オンライン会議の AI支援機能を大幅に強化した。
会議の文字起こし、要約、アクションアイテムの自動抽出に加え、参加者の発言分析や議事録の自動生成機能が追加された。リアルタイムでの質問応答支援や、会議後のフォローアップタスクの自動作成も可能になり、会議の生産性向上と効率化が期待される。
15. Google CloudでAIエージェント決済の新プロトコル「AP2」発表
GoogleがAIエージェント向けの新決済プロトコル「Agent Payments Protocol(AP2)」を発表した。
60社以上の企業と協力して開発され、AIエージェントがユーザーに代わって安全に決済を実行できる仕組みを提供する。デジタル契約である「Mandates」により暗号化署名された改ざん防止記録を作成し、取引の正当性を保証する。従来のカード決済から暗号資産まで幅広い支払い方法に対応している。
16. Alibabaが「Qwen3-Next」発表
中国のAlibabaが次世代大規模言語モデル「Qwen3-Next」を発表した。
前世代のQwen2.5から大幅な性能向上を実現し、推論能力、数学的計算、多言語処理において顕著な改善を見せている。特にコーディング能力と科学的推論において競合モデルを上回る性能を発揮する。オープンソース版も提供予定で、企業や研究機関での活用が期待される。中国のAI技術の国際競争力向上を示す重要な発表といえる。
17. OpenAI、ChatGPTに未成年向け制限を実施
OpenAIがChatGPTに18歳未満のユーザー向けの新たな制限機能を導入した。
未成年者のプライバシー保護と安全性確保のため、不適切なコンテンツへのアクセス制限や個人情報の取り扱いに関する厳格な管理を実施する。保護者による監督機能も強化され、利用時間の制限や特定機能へのアクセス管理が可能になった。教育分野での安全なAI活用を促進する重要な取り組みである。
18. OpenAIとJony Iveのハードウェア戦略
OpenAIと元AppleデザイナーのJony Iveが協力してAIハードウェア開発を進めている。
Appleからデザイナーを引き抜き、主要サプライヤーとの連携を強化してハードウェア事業への本格参入を目指す。スマートフォンやタブレットに代わる新しいAIデバイスの開発が噂されており、直感的なユーザーインターフェースと高度なAI機能を組み合わせた革新的な製品の登場が期待される。
19. GUGAが生成AI活用事例データベース公開
生成AI活用推進コンソーシアム(GUGA)が企業や組織における生成AI活用事例をまとめたデータベースを公開した。
様々な業界での実践的な活用例を収集し、導入効果や課題についても詳細に記録している。企業規模や業種別の検索機能を備え、自社での生成AI導入を検討する企業にとって貴重な参考資料となる。日本国内での生成AI普及促進と実用化加速を目的とした重要な取り組みといえる。
20. 生成AIが家族や親友を超える相談相手に
最新の調査により、多くのユーザーが生成AIを家族や親友よりも信頼できる相談相手として活用していることが判明した。
24時間利用可能で判断を下さない中立的な存在として、プライベートな悩みやキャリア相談に利用される傾向が強まっている。特に若年層では人間関係の悩みや将来の不安について生成AIに相談する割合が高く、人間とAIの関係性に新たな変化をもたらしている。
21. AIエンジニアがコンサルタントとして高報酬を獲得中
AI技術に精通したエンジニアがコンサルタントとして企業から高額報酬を得るケースが急増している。
企業のAI導入プロジェクトやデータ統合において専門知識を持つエンジニアの需要が高まり、時給数万円規模の案件も珍しくない。特に大手コンサルティングファームでは、AI専門知識を持つフリーランスエンジニアとの契約を積極的に進めており、従来のエンジニア市場に新たな価値創造の機会をもたらしている。
教育的観点から分析して注目すべき機能は?
まず、Google NotebookLMの学習支援機能拡充です。
フラッシュカードとクイズ機能の追加により、従来の講義型学習から能動的な学習スタイルへの転換が促進されます。教材をアップロードするだけで自動的に理解度チェックツールが生成されるため、塾や学校での個別指導が効率化されるでしょう。
次に、ChatGPTのThinking機能における思考時間の調整機能です。
学習者の理解レベルに応じて「軽め」から「深い」まで4段階の思考モードを選択できるため、基礎問題から応用問題まで段階的な学習支援が可能になります。
また、Notion 3.0のAIエージェント機能は、最大20分間にわたって複数ページの情報を分析・整理する能力を持ちます。
これにより、学習記録の自動整理や、過去の学習データから個別の学習計画を作成することが可能となり、パーソナライズ教育の実現に大きく寄与すると考えられます。
これらの技術は、教育現場における個別最適化学習と効率的な学習管理の両面で革新をもたらす可能性があるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
