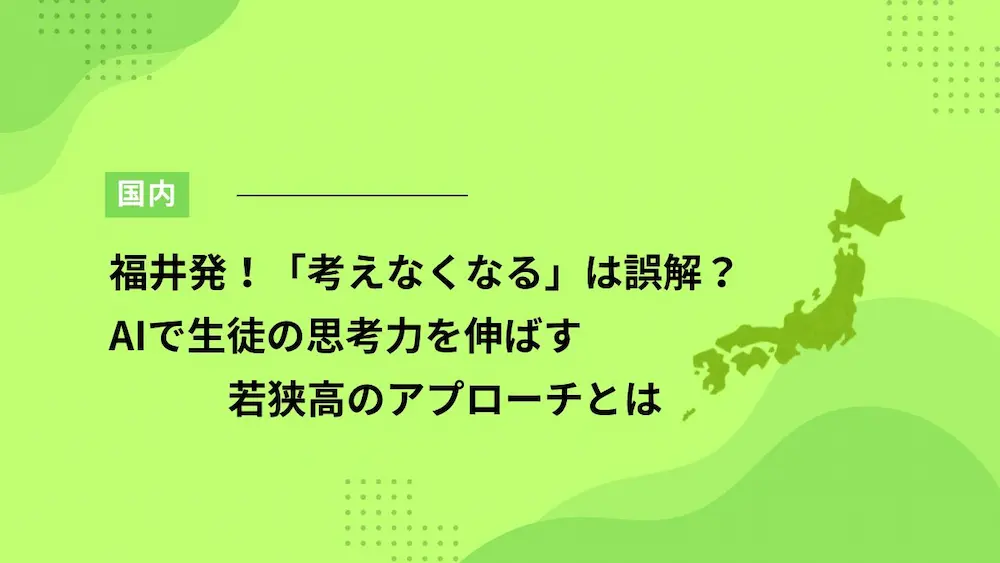
生成AIの教育現場導入で「生徒が自分で考えなくなる」という懸念が広がる中、福井県立若狭高校では全く異なる視点でMicrosoft Copilotを活用しているようです。
同高・校長は、AIとの対話を「異質なものとの出会い」と位置づけ、むしろ思考を深める触媒として捉えています。
重要なのは効率化ではなく「何を問うか」という問いの質であり、うまくいかない経験こそが学びの本質だと強調します。
探究学習で全国トップクラスの実績を持つ同校が示す、AI時代の新しい教育のあり方とは何でしょうか。
【記事の要約】
福井県立若狭高等学校(福井県小浜市)の渡邉久暢校長は、生成AIを教育に活用する新たな方向性を提示している。
同校が掲げる「異質なものとの対話」を重視する教育理念のもと、Microsoft Copilotとの対話を「異質なものとの出会い」として位置づけ、生徒の思考力向上と人格形成に活かそうとしている。
従来の効率化重視の生成AI活用ではなく、「何を問うか」という問いの質を重視し、AIとの試行錯誤を通じて思考を深める学びを目指す。
生成AIが提供する「うまくいかない経験」こそが、生徒の言語化能力や問い直しの力を育成する機会であると捉える。
教師の役割についても、単なる業務効率化ツールとしてではなく、「揺らぎのある情報」に対話することで授業観を問い直し、教育的価値を見出すことの重要性を強調している。
(出典元:2025年9月17日 こどもとITより)
今後の学校教育への応用と可能性は?
この若狭高校の取り組みは、今後の学校教育において重要な示唆を与えています。
まず、生成AIを単なる作業効率化ツールではなく、思考を深める「触媒」として活用する視点は、探究学習や課題研究の質的向上につながる可能性があります。
教師の専門性向上の面では、AIとの対話を通じて自らの教育観や授業観を問い直すプロセスが、継続的な研修機会として機能することが期待されます。
特に「言葉の力」を重視する視点は、適切なプロンプト設計能力の育成として、教師研修の新たな柱となるでしょう。
生徒の学習面では、AIとの対話で「うまくいかない経験」を積み重ねることで、メタ認知能力や問い直す力が育成される可能性があります。
また、生徒自身が評価基準を言語化し、自己評価を深める実践は、主体的学習者の育成に大きく貢献すると考えられます。
情報元はこちらからご覧ください。
https://edu.watch.impress.co.jp/docs/topic/special/2043969.html
