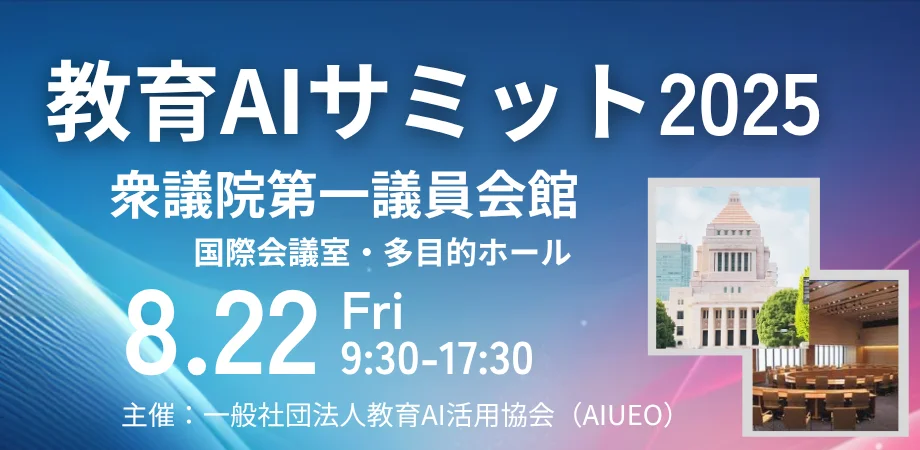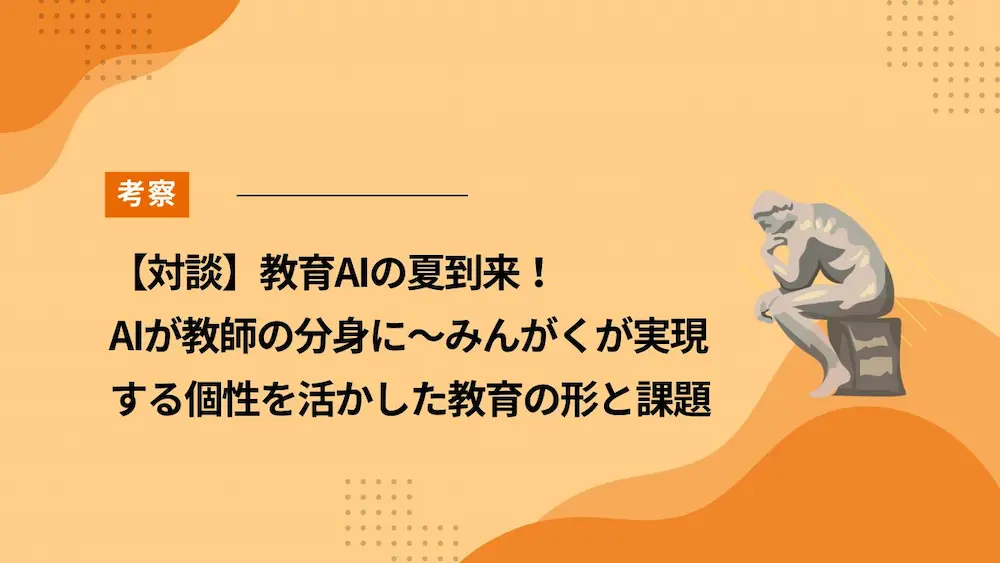
教育AIサミット2025(8月22日・衆議院第一議員会館)等の企画開催が活発な8月に突入しました。
学校現場でのAI活用が本格化する中で、「先生一人ひとりの教え方を再現するAI」という革新的な技術が注目を集めています。
みんがくが開発するシステムは、教師の口癖や関西弁まで学習し、生徒の習熟度に応じてスピードや語彙を調整する「先生の分身」として機能。
月額990円という低コストで実現される個別最適化教育は、従来の画一的な指導を変革する可能性を秘めています。
しかし同時に、AI格差が新たな学力格差を生む懸念も指摘される今、教育現場の未来はどのような姿になるのでしょうか。
みんがくと教育AI活用協会(AIUEO)代表としても活動する佐藤雄太氏と、実用英語推進機構の安河内哲也氏の対談から、学校教育の転換点を探ってみましょう。
【対談の要約】
株式会社みんがく代表の佐藤雄太氏と安河内哲也氏の対談では、教育現場におけるAI活用の現状と課題が語られた。
佐藤氏は教育AI活用協会(AIUEO)も運営し、教育向けAIサービスを展開している。
みんがくの最大の特徴は、先生一人ひとりの教え方や個性をAIに反映できることである。
通常のChatGPTでは毎回詳細な指示が必要だが、同社では教師の指導スタンスや口癖、関西弁などの特徴を「モード」として設定可能にした。
生徒の習熟度に応じて語彙制限やスピード調整も行える。
月額990円という低コストで、英会話から英作文添削まで対応し、アバター機能により先生の分身のような体験も提供する。
教師は生徒の対話ログを確認でき、個別最適化されたフィードバックが可能。
現在は教育機関向け(BtoB)での提供が中心で、全教科対応の100種類のテンプレートを用意している。
一方で、AI活用格差が学力格差に直結する懸念も指摘されており、誰もが使える環境整備が急務である。
(出典元:2025年7月23日 安河内哲也 情報発信ノート BRAIN HUB ONLINEより)
今後の学校教育への活用と可能性は?
この対談から見える教育の未来は、生成AIが単なる補助ツールを超えて「教師の分身」として機能する可能性です。
個別最適化教育の実現において、従来は物理的に困難だった「全生徒への手厚いサポート」がAIによって可能になります。
特に注目すべきは、教師の個性や指導スタイルを保持しながらAIが支援する点です。
これにより、教師らしさを失うことなく効率化が図れ、より創造的な授業設計に時間を割けるようになるでしょう。
また、対話ログの可視化により、生徒の学習過程を詳細に把握でき、つまずきポイントの早期発見と個別対応が実現します。
しかし最重要課題は「AI格差の解消」です。
経済状況や地域格差によってAI活用に差が生じれば、学力格差がさらに拡大する恐れがあります。
そのため、公教育でのAI環境整備や教師のAIリテラシー向上が急務となります。
将来的には、すべての生徒が自分専用のAI学習パートナーを持ち、24時間いつでも個別指導を受けられる環境が実現するかもしれません。
教育の民主化と質の向上を両立させる鍵がここにあり…でしょうか。
今回の対談の全文はこちらからご覧ください。
https://note.com/yasukochi2020/n/nf483d5607439
また、教育AI活用協会(AIUEO)の今夏の企画開催はこちらから確認ください。
8月14日 KOBE AI サマーフェスティバル 2025
8月22日 教育AIサミット2025