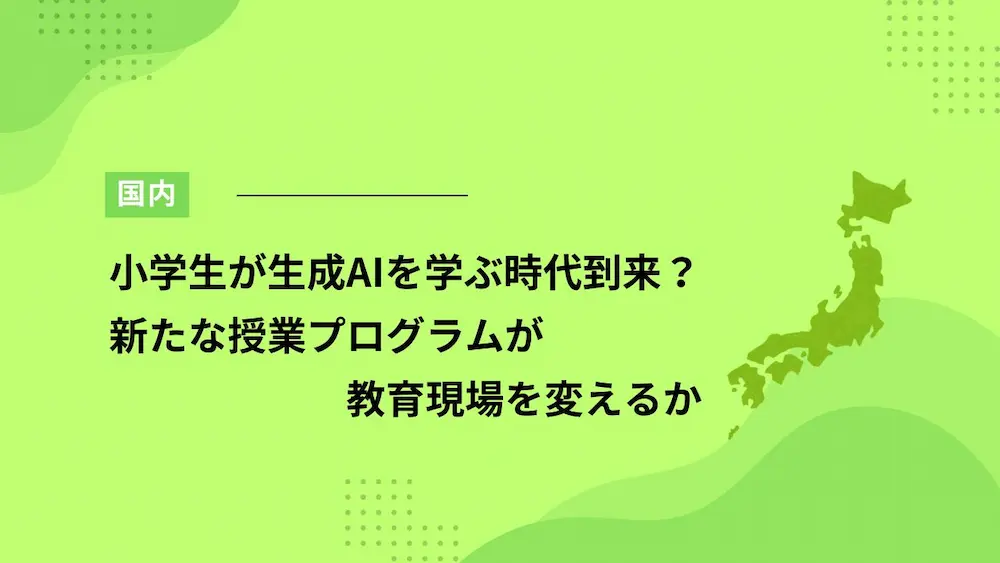
10歳の子どもの約7割がスマートフォンでインターネットに接続する現代、教育現場では新たな課題が浮上しています。
NPO法人企業教育研究会が開発した小学生向け授業プログラム「生成AIって何だろう?」は、まさにこの時代の要請に応える取り組みです。
45分間の授業で、小学5・6年生が生成AIの仕組みから活用方法、注意点まで体系的に学べるこのプログラムは、単なる技術の使い方を教えるのではなく、「AIと共に生きる」ための土台を築くことを目指します。
地域格差なく質の高いAI教育を実現する可能性を秘めていますが、教育現場をどう変えるのでしょうか。
【記事の要約】
NPO法人企業教育研究会(千葉県千葉市)は、アクセンチュア株式会社の支援を受けて、小学生向け授業プログラム「生成AIって何だろう?」を開発した。
このプログラムは2025年6月24日に発表され、6月からパイロット授業が実施されている。
開発の背景には、生成AIの急速な社会浸透がある。
ChatGPTの登場以降、生成AI機能を搭載したパソコンやスマートフォンが普及し、こども家庭庁の調査によると10歳の子どもの66.7%がスマートフォンでインターネットに接続している現状がある。
このため、小学生のうちから生成AIの基本的な仕組みや特徴、活用方法を理解することがAIと共存していく上で重要となっている。
授業プログラムは小学校5・6年生を対象とした45分間の内容で構成。
主な内容は、日常生活の事例を通じたAIの基礎学習、講師によるプロンプト入力の実演を通した生成AIの可能性の理解、「苦手な学習の克服方法」をテーマとしたプロンプト作成のコツの習得、そして情報の正確性や著作権に関する注意点の考察である。
文部科学省のガイドラインでは、「生成AI自体を学ぶ場面」「使い方を学ぶ場面」「各教科等の学びにおいて積極的に用いる場面」を組み合わせた教育の重要性が強調されている。
本プログラムは、単に生成AIを使用するだけでなく、その仕組みを理解し、子どもたち自身が適切に活用できる力を身につけることを目的としている。
同会では、対面での出張授業に加え、全国の教員が活用できるダウンロード教材としての展開も準備しており、また今後は報道関係者向けの授業公開も予定し、生成AIリテラシー教育の普及を目指している。
(出典元:2025年6月24日 PR TIMES、同24日 こどもとITより)
今後の学校教育への活用と将来の可能性は?
このプログラムは、今後の学校教育において極めて重要な意味を持つでしょう。
まず、デジタルネイティブ世代の子どもたちが生成AIを適切に活用するためのリテラシー教育の基盤となります。
単なる技術の使い方ではなく、AIの仕組みを理解し、情報の真偽を判断する力を育成することで、批判的思考力の向上にも寄与します。
将来的には、このような教育プログラムが全国の小学校に普及することで、AI時代に対応した人材育成が可能になります。
子どもたちがAIを「使いこなす」だけでなく「AIと共に生きる」ための土台を築くことで、創造性と論理的思考を兼ね備えた次世代の育成が期待されます。
また、教員向けのダウンロード教材の提供により、地域格差なく質の高いAI教育が実現できる可能性があります。
これらの取り組みは、日本の教育現場におけるDX推進の新たな一歩となり、国際競争力のある人材育成にも貢献するでしょう。
