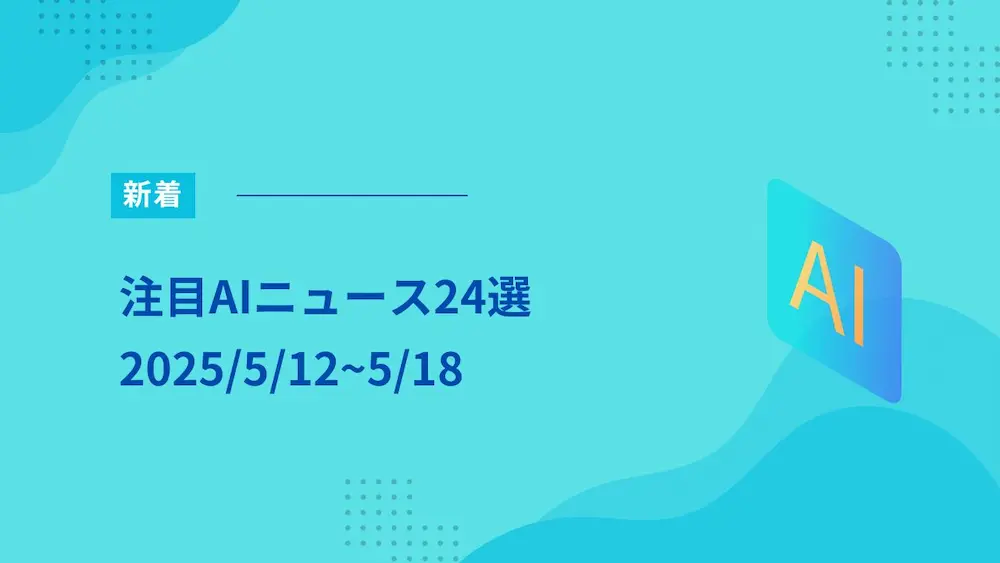
最新の生成AIニュース(2025年5月12日~5月18日)を、YouTubeチャンネル「いけともch_旧リモ研」の池田朋弘氏が注目した24のキーワードでご紹介します。
1. OpenAIがコーディングエージェント「Codex」を発表
OpenAIが新たなコーディングエージェント「Codex」を発表した。
GitHubリポジトリと連携し、プログラムの説明や修正を並列で依頼できる。作業を小分けにして同時に進行させる新しい仕事スタイルを実現し、処理速度も速い。将来的にはエンジニア以外のホワイトカラー業務にも同様の概念が適用される可能性がある。
2. OpenAIのGPT-4.1をChatGPTに統合~開発者向け機能強化
OpenAIがGPT-4.1をChatGPTに統合した。モデル選択画面でGPT-4.1とGPT-4.1 miniが選択可能になり、GPT-4 miniは廃止された。
GPT-4.1は100万トークンまで読み込め、コーディング能力も向上している。ベンチマークでも高評価だが、劇的な進化というよりはベースモデルの性能向上という印象だ。
3. ChatGPTにPDFエクスポート機能追加で企業利用を本格支援
ChatGPTのDeep Research機能にPDFエクスポート機能が追加された。リサーチ結果をリンクや画像を含めたままPDF形式で出力できるようになり、ビジネス利用が格段に便利になった。
Plus、Team、Proプランで利用可能で、EnterpriseとEduプランにも近日提供予定。メールでの添付や資料としての共有が容易になり、業務効率が向上する。
4. GeminiがGitHub連携を開始
Google GeminiがGitHub連携機能を開始した。個人のアドバンスプラン以上で利用可能で、設定からGitHubアカウントと連携してリポジトリを読み込める。
コードの内容理解や改善提案が可能になり、プログラミング作業の効率が向上する。ChatGPTも同様の機能を持つが、モデルによる得手不得手があり、選択肢が増えたことでユーザーの利便性が高まった。
5. Geminiアプリのファイルアップロード機能を強化
Google Geminiアプリのファイルアップロード機能が強化され、1回のプロンプトで最大10ファイルまでアップロード可能になった。
また、Gemと呼ばれるGPTs相当の機能でも最大10個の知識をアップロードできるようになった。Geminiは大容量データの処理に優れており、アップロードしたファイルの内容を正確に把握し、質問に対して適切な回答を提供する。
6. GeminiのCanvasでプレビューが可能に
Google GeminiのCanvasモードにプレビュー機能が追加された。作成したHTMLコードをその場で確認できるようになり、Googleワークスペースプランでも利用可能。
最近のアップデートでコーディング能力も向上しており、情報の可視化や整理をその場で行い、すぐに結果を確認できる。SVG画像やマーメイドのプレビューには未対応だが、Gemでモデル選択も可能になり利便性が向上した。
7. GoogleがAndroidとChromeのアクセシビリティ機能を強化
GoogleがAndroidとChromeのアクセシビリティ機能を強化した。TalkBackとGeminiの連携により、視覚障害者が画像や画面の内容を質問できるようになった。
ChromeではPDFのOCR機能が向上し、スキャンされた文書もスクリーンリーダーで読めるようになった。Android版Chromeにはページズーム機能が追加され、レイアウトを崩さずテキストサイズを拡大できる。
8. Notionの業務向けAI統合機能「Notion AI for Work」を発表
NotionがAI統合機能「Notion AI for Work」を発表した。エンタープライズサーチ機能でSlackやGoogleドライブと連携した検索が可能になり、AIミーティングノートでは会議内容をリアルタイムで文字起こしして要約する。
リサーチモードでWeb情報やNotion内データを検索して回答を生成する。音声データは保存せず文字起こしと要約のみを残すため、プライバシーにも配慮されている。
9. MapifyにおいてZapierでの自動生成が可能に
Mapifyがノーコードツールのプラグイン連携を強化し、Zapierでの自動生成が可能になった。Zapierのワークフローを通じて、データを自動的にMapifyのマップに反映させることができる。
例えばGoogleスプレッドシートの住所情報から自動的にマップを生成するなど、データ可視化の効率が大幅に向上した。今後はさらに多くのノーコードツールとの連携が予定されている。
10. ReplitのAI開発向け機能を安全・実用レベルに強化
ReplitがAI開発支援機能「Vibe Coding」を大幅に強化した。コード生成の精度が向上し、実用レベルの安全性を確保。特にセキュリティ面での改善が顕著で、脆弱性のあるコードを生成しにくくなった。
また、コンテキスト理解力が向上し、プロジェクト全体を把握した上での適切な提案が可能になった。開発者の生産性向上と品質確保の両立を実現している。
11. Contextual AIがRAG向けの高精度ドキュメントパーサー発表
Contextual AIがRAG(検索拡張生成)向けの高精度ドキュメントパーサー「Document Parser」を発表した。複雑なレイアウトの文書でも正確に構造を把握し、テーブルやグラフなどの情報を適切に抽出できる。
特に金融や法律文書の処理に強みを持ち、従来のパーサーと比較して30%以上の精度向上を実現。RAGシステムの品質向上に大きく貢献する技術だ。
12. You.comが企業向けAIリサーチを発表
You.comが企業向けAIリサーチツール「ARI Enterprise」を発表した。社内データとインターネット情報を組み合わせた高精度な検索と回答生成が可能。
特に引用の正確性に重点を置き、情報の出所を明確にしながら回答を生成する。企業のナレッジベースと連携し、社内の専門知識を活用した回答も提供できる。セキュリティ面も強化され、機密情報の適切な取り扱いを保証している。
13. TikTokがAIで写真を動画化する新機能を導入
TikTokが静止画を動画化する新機能「AI Alive」を導入した。ユーザーが投稿した写真に自然な動きを加え、短いアニメーションクリップに変換する。
背景の揺れや人物の微妙な表情変化など、リアルな動きを生成できる。この機能はクリエイターのコンテンツ制作の幅を広げ、より魅力的な投稿を可能にする。プライバシーに配慮し、顔認識には明示的な許可が必要となっている。
14. 企業向けAI検索エンジン「Felo Enterprise」を提供開始
企業向けAI検索エンジン「Felo Enterprise」の提供が開始された。社内文書や業界データを学習し、専門的な質問に正確に回答できる。
従来の検索エンジンと異なり、質問の意図を理解して関連情報を総合的に分析し、要約された回答を提供する。また、情報源の透明性を確保し、回答の根拠を明示する機能も備えている。導入企業では情報検索時間が平均40%削減されたという実績がある。
15. KlarnaがAI方針を転換してカスタマーサービスに再び人間採用
決済サービス大手のKlarnaがAI方針を転換し、カスタマーサービスに人間のオペレーターを再び採用することを発表した。
AIのみでは解決できない複雑な問題や感情的なケアが必要な場面で、人間の対応が求められることが判明。AIと人間のハイブリッド体制により、顧客満足度が15%向上したという。AIは定型業務を効率化し、人間はより複雑で価値の高い対応に集中するという新たな協業モデルを構築している。
16. Sales MarkerがAI業務支援サービスをリリース
Sales MarkerがAI業務支援サービス「Sales Marker スーパーエージェント」をリリースした。営業活動に特化したAIが顧客データを分析し、最適なアプローチ方法や商談のタイミングを提案する。
また、過去の成功事例を学習し、類似案件での成功確率を高める戦略を自動生成する。CRMとの連携により、データ入力の手間を削減しながら、営業パフォーマンスを向上させる総合的なソリューションとなっている。
17. ChatGPTが「ユーザーの人生すべて」を記憶する未来へ
OpenAIのCEOであるSam Altmanが、ChatGPTが「ユーザーの人生すべて」を記憶する未来について言及した。将来的にはユーザーの過去の会話だけでなく、日常生活のあらゆる情報を記憶し、パーソナライズされた支援を提供する構想だ。
プライバシーとセキュリティの課題を認識しつつも、ユーザーの許可を得た上で個人の文脈を理解したAIアシスタントの実現を目指している。実現すれば業務効率や生活の質が飛躍的に向上する可能性がある。
18. GoogleがAndroid AutoにAIアシスタントを導入
GoogleがAndroid AutoにAIアシスタント「Gemini」を導入した。運転中でも自然な会話で複雑な指示が可能になり、ナビゲーションやメッセージ送信、音楽再生などをシームレスに操作できる。
特に注目すべきは文脈理解能力で、連続した質問にも適切に対応する。また、運転状況を考慮した情報提供や、車内環境の調整も音声で行える。安全性を重視し、運転に集中できるよう視覚的な情報は最小限に抑えられている。
19. DeepMindがGemini搭載のAIエージェントを発表
GoogleのDeepMindがGemini搭載のAIエージェント「AlphaEvolve」を発表した。このエージェントは自己進化能力を持ち、与えられたタスクに対して最適な解決策を自ら学習・改善していく。
特にプログラミングやデータ分析の分野で高い能力を発揮し、人間が考えつかなかった効率的なアルゴリズムを生み出す事例も報告されている。複雑な問題を段階的に分解し、最適解を見つける能力は従来のAIを大きく上回るものだ。
20. マイクロソフトとOpenAIが今後の提携を再交渉か
マイクロソフトとOpenAIが提携条件の再交渉を検討しているという情報が浮上した。
現在の契約ではマイクロソフトがOpenAIの利益の一部を得る権利を持つが、OpenAIの急速な成長に伴い、より対等なパートナーシップへの移行が模索されている。両社の関係変化はAI業界全体の勢力図に影響を与える可能性があり、特にAzureプラットフォームとOpenAIモデルの統合に関する今後の展開が注目される。
21. Sequoiaがエージェント経済の到来を予測
ベンチャーキャピタルのSequoiaが「エージェント経済」の到来を予測するレポートを発表した。AIエージェントが人間に代わって意思決定や取引を行う新たな経済圏が形成されつつあるという。
特に注目すべきは、エージェント同士が自律的に交渉・取引するシステムの出現で、これにより市場の効率性が飛躍的に向上すると予測している。今後5年以内にエージェント経済は1兆ドル規模に成長する可能性があるとしている。
22. AmazonがAI時代における「新しい人間の仕事像」提示
Amazonが「AI時代における新しい人間の仕事像」に関する包括的なレポートを発表した。AIが定型業務を担う中で、人間は創造性、倫理的判断、対人関係構築などの領域で価値を発揮するとしている。
特に「AIオーケストレーター」という新たな職種の重要性を強調し、複数のAIシステムを連携させて複雑な問題を解決する人材の需要が高まると予測。Amazonは社内でもこの方針に基づいた人材育成プログラムを開始している。
23. 東京都の全都立学校で生成AI活用を本格導入
東京都が全都立学校での生成AI活用を本格導入することを発表した。教員の業務効率化と生徒の情報リテラシー向上を目的としており、授業計画の作成や個別学習支援にAIを活用する。
特徴的なのは「AIリテラシー」を必修科目として設置し、AIの仕組みや適切な活用法、限界についても学ぶ点だ。プライバシー保護のためのガイドラインも整備され、生徒の個人情報を含むデータの取り扱いには厳格なルールが設けられている。
24. チューリッヒ大学によるAIの説得力実験
チューリッヒ大学の研究チームがAIの説得力に関する実験結果を発表した。同じ内容でも、人間が書いた文章とAIが生成した文章では、読者の受け取り方に明確な違いがあることが判明した。
特に専門的な内容においては、AIが生成した文章の方が論理的で説得力があると評価される傾向が見られた。この結果は、情報源の信頼性評価の新たな課題を提起しており、メディアリテラシー教育の重要性を再認識させるものとなっている。
生成AIが変える?教育現場への影響いかに
生成AIの急速な進化により、日本の教育現場でも革新的な活用法が広がりつつあります。
特に注目なのは、東京都が全都立学校で生成AI活用を本格導入する動きでしょう。
この取り組みは、教員の業務効率化と生徒の情報リテラシー向上を目的としており、「AIリテラシー」を必修科目として設置する点が特徴的です。
また、Notion AIの「AI for Work」のようなツールは、教育現場でも大きな可能性を秘めています。
例えば、授業内容をリアルタイムで文字起こしし要約する機能は、教員の授業記録作成の負担を軽減するだけでなく、欠席した生徒への情報提供にも活用できます。
他にも、Google GeminiのCanvasモードやファイルアップロード機能の強化は、教材作成や情報の可視化に役立ちます。
複数のファイルを一度に分析できる機能は、生徒の提出物を効率的に確認する際に威力を発揮するでしょう。
さらに、GoogleのAndroidとChromeのアクセシビリティ機能強化は、特別支援教育において大きな意味を持ちます。
TalkBackとGeminiの連携により、視覚障害のある生徒も画像や画面の内容を理解しやすくなります。
これらのAI技術を教育現場に導入することで、個別最適化された学習支援や教員の業務効率化が進み、より質の高い教育環境の構築が期待できます。
ただし、プライバシー保護や適切な活用法についての指導も同時に行うことが重要です。
生成AIは道具であり、それを教育目的に沿って適切に活用するための知識とスキルを育むことこそが、これからの教育に求められています。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
