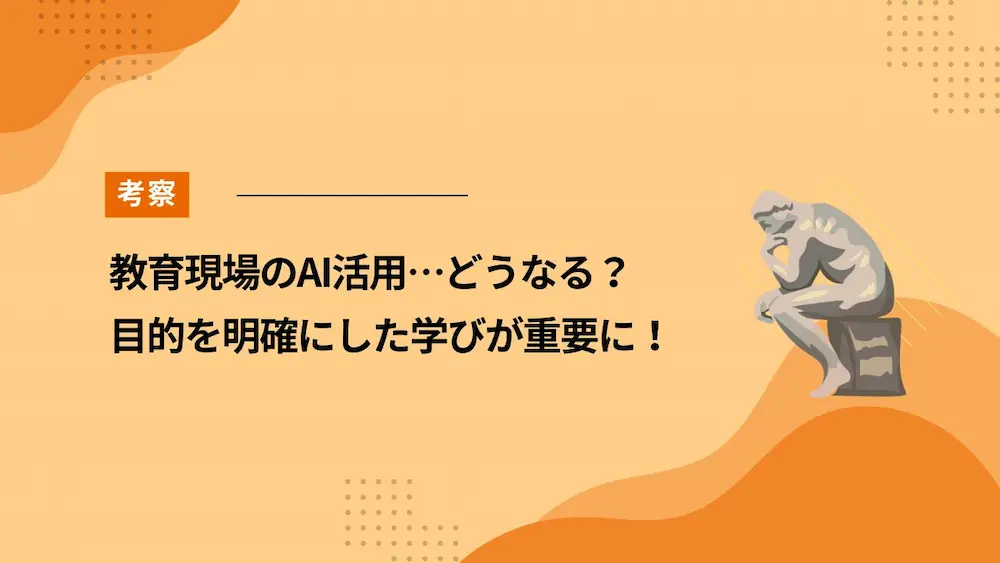
教室にAIが入り込む時代において、単なる便利ツールを超えた可能性が見えてきた。
今年3月23日の「教育AIサミット 実例大全」で紹介された先進事例からは、生成AIが子どもたちの創造性を解放し、学びを個別最適化する強力なパートナーとなりうる姿が浮かび上がる。
プログラミングに集中できなかった生徒が夢中になり、文章表現に困難を感じていた児童が自信を持って意見を述べるようになった実践例から、AIと教育の新たな関係性を探る。
【記事の予約】
2025年3月にコクヨ東京品川オフィス THE CAMPUSにて開催されたイベント「教育AIサミット 実例大全」(主催:一般社団法人教育AI活用協会)で紹介された事例から、生成AIが教育現場で学びの個別最適化や創造性向上、思考力支援の強力なツールとなる可能性が示された。
青山学院中等部の安藤昇氏は「バイブコーディング」と呼ばれる手法を紹介。
生徒が自然言語で「なんとなく」作りたいものを指示するとAIがコード生成から動作確認まで行うプログラミング手法だ。
従来のプログラミング学習で集中力が続かなかった生徒も、この手法では長時間集中して取り組むようになった。
東京学芸大学附属小金井小学校の鈴木秀樹氏は、国語の授業でAIを活用した個別最適化の実践を紹介した。
「作品の魅力を文章でまとめる」活動で書くことに困難を感じる児童に対し、AIとの対話を通じて考えを整理し文章化を支援。
鈴木氏は「授業の目的設定」の重要性を強調し、「友達と話し合い考えを広げること」が目的であり、文章作成はその手段に過ぎないと位置づけた。
両氏の実践から、AIは単なる作業代行ではなく、生徒のアイデアを形にし可能性を広げる「パートナー」となり得ることが示された。
一方で、高性能化したAIによって中高生でも容易に高度な技術にアクセスできる状況が生まれており、倫理教育の重要性も浮き彫りになった。
(出典元:2025年5月13日 こどもとITより)
今後の学校教育への示唆と可能性は?
AIを教育に活用する際には、常に授業の目的を明確にすることが重要です。
文章を書くことが目的なのか、話し合うことが目的なのかによって、AIの位置づけが変わります。目的が明確であれば、AIは有効な学習支援ツールとなります。
また、AIによって「正解を効率よく導き出す力」から、「多様な情報をもとに最適解を見出す力」へと求められる能力がシフトしていく可能性があります。
AIでは答えを出せない”答えのない問い”に対して思考する力を育むことが、今後の教育では一層重要になるでしょう。
さらに、AIは学習上の困難を抱える子どもたちの支援ツールとしても大きな可能性を秘めています。従来は意見表明が難しかった児童も、AIの助けで自信を持って話し合いに参加できるようになるなど、インクルーシブ教育の観点からも注目されます。
将来的には、AIを「道具」そして「パートナー」として位置づけ、子どもたち自身が主体的に学び方を選択できる環境づくりが進むでしょう。
教員はAIの特性を理解した上で最適な使い方を模索し、人間中心の視点で教育の本質に立ち返ることが求められます。
今回の出典元となった記事全文は下記からご覧になれます。
https://edu.watch.impress.co.jp/docs/report/2012293.html

