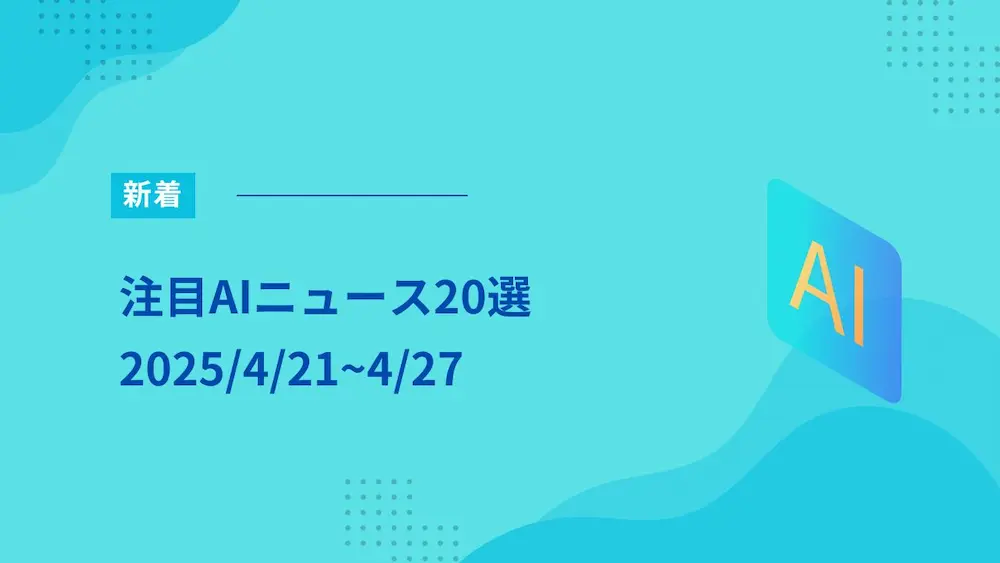
最新の生成AIニュース(2025年4月21日~27日)を、「いけともch_旧リモ研」の池田朋弘氏が注目した20のキーワードでご紹介します。
1. OpenAIがChatGPT deep research toolの軽量版を発表
OpenAIがChatGPTのディープリサーチ機能の軽量版を無料ユーザー向けに提供開始した。
O4という軽量モデルを採用することで、無料版でも月5回程度の利用が可能となった。有料版と比較すると回答内容はやや簡素だが、情報検索の可能性を体験できる。また、プラスやチームプランではO3やO4モデルの利用回数が約2倍に増加している。
2. OpenAIがChatGPTの画像生成モデル「gpt-image-1」提供
OpenAIがChatGPTの画像生成モデル「gpt-image-1」をAPI経由で提供開始した。
これまではChatGPT内でしか使えなかった「ジブリ風画像」で話題の機能が、プログラムから直接利用可能になった。100万トークンあたり40ドル(約1枚230円程度)で利用でき、背景透過やサイズ・品質の指定も可能になり、導入から1週間で7億枚以上が生成された人気機能だ。
3. Perplexity iOSアプリに音声AIアシスタント搭載
PerplexityがiOS向けアプリに高度な音声AIアシスタント機能を追加した。
iPhone 8以降のデバイスで利用可能で、情報検索やリマインダー設定、メール作成、カレンダー予定追加、音楽再生、地図案内などを音声で操作できる。Apple MusicやApple Mailとの連携も標準搭載。GPT-4oやClaude 3.7 Sonnetなど複数の先端AIモデルを組み合わせており、Apple Intelligence未対応機種でも高度なAI体験を提供する。
4. Gammaが2.0プラットフォームをリリース
プレゼンテーション作成AIのGammaが2.0にアップデート。生成される内容のレベルが向上し、画像編集機能が大幅に強化された。
特筆すべき新機能として、静止画を動画化する機能や背景ぼかし機能、多様なレイアウトパターンを視覚的に選択できるインターフェースが追加された。すでに5000万人以上のユーザーを抱え、プレゼンテーション作成の効率と品質を大きく向上させている。
5. Adobe Fireflyに動画生成強化&モバイル版登場
Adobe Fireflyが大幅アップデートし、画像生成モデルの強化や動画生成機能の拡充、モバイルアプリ版の提供開始を発表した。
新モデル「Image 4」と「Image 4 Ultra」が登場し、特にUltraは高解像度でも品質を維持する。ベクター画像生成にも対応し、イラストレーターなどでパーツごとの編集が可能になった。また、テキストから動画生成や画像から動画生成機能も強化され、iOSとAndroid向けアプリも近日リリース予定。
6. ハローワークのネットサービスにAI活用、厚労省が実証実験
厚生労働省がハローワークのオンラインサービスにAIを活用する実証実験を開始した。
月間7,000万アクセスを誇るサービスで、利用者の質問に自動応答するAIチャットと、求職者のニーズと求人情報のマッチング精度向上の2つの用途でAIを導入する。特にマッチング機能では、AIが求職者の情報を分析し、適切な求人を推薦するとともに、その理由も説明することで就職活動の効率化を図る取り組みである。
7. AnthropicがチャットAIの悪用事例と対策レポートを公開
AnthropicがAIアシスタント「Claude」の悪用事例と対策に関する詳細レポートを公開した。
主な悪用パターンとして、①AIを使った偽SNSアカウント運用による特定思想の拡散、②パスワード解読ツールの作成、③多言語での求人詐欺コンテンツ作成、④マルウェア開発支援、の4種類を特定した。
特に偽SNSアカウントは高度に擬人化され、投稿だけでなく、いいねやコメントなどの行動もAIが判断している。Anthropicはこれらの不正利用に対するアカウント停止や検知精度向上に取り組んでいる。
8. 論文「AI2027」が24か月で人間レベルのAI達成を予測
「AI2027」と題された論文が大きな注目を集めている。著者らは今後24か月以内に人間レベルの汎用人工知能(AGI)が達成される可能性が高いと予測した。
この予測は現在のAIモデルの進化速度と計算能力の増加傾向に基づいている。特に注目すべきは、AIの能力が指数関数的に向上している点と、すでに一部分野では人間を超える性能を示している事実である。論文は技術的な観点だけでなく、社会的影響についても言及している。
9. 論文AI2027への反響と著者コメントについて
「AI2027」論文は発表後、AI研究コミュニティから様々な反応を引き起こした。賛同派は計算能力の増加と大規模言語モデルの急速な進化を根拠に支持を表明。
一方で批判派は人間の知能の複雑さを過小評価していると指摘している。論文著者は追加コメントで、「予測は確率的なものであり、24か月という期間はあくまで現在の進化速度に基づく推計である」と強調。また、AGI実現に向けた課題として、因果推論や長期的計画能力の向上が必要だと言及している。
10. Anthropic CEOが「解釈可能性の緊急性」を提唱
Anthropicの共同創業者兼CEOであるダリオ・アモデイ氏が「解釈可能性の緊急性」という概念を提唱。AIシステムの内部動作を理解することが安全性確保の鍵であると主張している。
特に高度なAIモデルが複雑化するにつれ、その判断プロセスのブラックボックス化が進行しており、予期せぬ挙動や安全上のリスクが生じる可能性を警告。Anthropicでは解釈可能性研究に多額の投資を行い、AIの意思決定過程を可視化する技術開発を進めている。
11. AnthropicがClaudeの実世界での価値観表現を分析
Anthropicが自社のAIアシスタント「Claude」の価値観表現に関する大規模分析結果を公開した。実世界の多様な質問に対するClaudeの回答を分析し、どのような価値観が反映されているかを調査した初の包括的研究である。
分析の結果、Claudeは一貫して人間の安全性を優先し、違法行為や有害行為の支援を拒否する傾向が強いことが判明。一方で文化的背景や政治的立場によって解釈が分かれる問題については、中立的な立場を維持しつつ多様な視点を提示する傾向が確認された。
12. Mozillaが「Any-Agent」ライブラリを公開
Mozillaが複数のAIアシスタントを統一的に操作できるオープンソースライブラリ「Any-Agent」を公開。
このライブラリを使用することで、開発者はOpenAI、Anthropic、Google、Mistralなど異なる企業が提供するAIモデルを同一のインターフェースで扱うことが可能になる。APIの違いを抽象化し、モデル間の切り替えを容易にすることで、特定のAIプロバイダーへの依存を減らし、最適なモデルを柔軟に選択できる環境を提供する。すでにPythonとJavaScriptに対応しており、今後も対応言語を拡大予定という。
13. Character.AIが動画生成AI「Avatar-FX」を公開
キャラクターAIプラットフォームのCharacter.AIが、テキストから動画を生成する新技術「Avatar-FX」を公開した。この技術はAIキャラクターの表情や動きを自然に生成し、テキスト入力だけで感情豊かな動画コンテンツを作成できる。
特筆すべき点は、生成された動画の品質の高さと、キャラクターの感情表現の自然さである。すでにベータ版が一部ユーザーに公開されており、クリエイターやエンターテインメント業界から高い関心を集めている。今後はリアルタイム生成機能も追加予定だ。
14. OpenAI Japan 1周年、COOが成果と次の1年を語る
OpenAI Japanが設立1周年を迎え、COOの田川欣哉氏が初年度の成果と今後の展望を語った。
日本法人設立から1年で、日本語対応の強化や国内企業との連携拡大など多くの成果を上げた。特に日本語での応答精度が大幅に向上し、日本企業向けのカスタマイズサービスも開始。次の1年では、日本の文化や社会的背景を深く理解するAIの開発と、日本企業のAI活用支援に注力する方針を示した。また、日本の教育機関との連携も強化し、次世代AI人材の育成にも貢献していく考えを明らかにしている。
15. ChatGPT Searchが欧州で急成長
OpenAIのChatGPT Searchが欧州市場で急速に成長していることが明らかになった。
欧州でのユーザー数は過去3か月で300%以上増加し、特にフランス、ドイツ、イタリアでの普及が著しい。この成長の背景には、欧州言語への対応強化と、地域特有の情報ニーズに応える検索精度の向上がある。
また、GoogleやBingなど既存検索エンジンからの乗り換えユーザーも増加傾向にある。OpenAIは欧州でのさらなる普及に向け、地域特化型の機能拡充と多言語対応の強化を進めている。
16. Geminiの月間アクティブユーザーが3.5億人と判明
Googleの最新AI「Gemini」の月間アクティブユーザー数が3.5億人に達したことが発表された。この数字はGoogleが四半期決算発表で明らかにしたもので、前四半期比で約30%の増加となる。
特にモバイルアプリ版の利用が急増しており、Android端末への標準搭載が普及を後押ししている。利用シーンとしては検索補助や文章作成、画像分析が上位を占め、教育分野での活用も増加傾向にある。Googleは今後、Geminiの機能をさらに拡充し、検索エンジンとの統合を強化する方針だ。
17. MicrosoftのCopilot利用停滞、AI戦略に陰り
Microsoftの主力AIアシスタント「Copilot」の利用者数が予想を下回り、成長が停滞していることが明らかになった。
初期の急速な普及後、継続的な利用率が低下傾向にあり、特に企業向けCopilot+プランの契約更新率に課題が生じている。この背景には、ユーザーの期待と実際の機能のギャップや、競合AIサービスの台頭がある。
Microsoftは対策として、Office製品との統合強化や、業種別に特化した専門機能の追加を計画。また、ユーザーインターフェースの改善にも注力し、利用障壁を下げる取り組みを進めている。
18. OpenAIがGoogle Chrome買収に意欲
OpenAIがGoogle Chromeブラウザの買収に関心を示していることが報じられた。
複数の情報筋によると、OpenAIのサム・アルトマンCEOはGoogleの親会社Alphabetに対し非公式に打診を行ったという。この動きはOpenAIがAI検索事業を強化する戦略の一環と見られており、世界シェア65%を誇るChromeを獲得することで、AIアシスタントの普及基盤を一気に拡大する狙いがある。
ただし、Googleはこの提案に否定的な姿勢を示しており、独占禁止法の観点からも実現のハードルは高いとの見方が強い。
19. 中国AIスタートアップManusが7500万ドル調達
中国のAIスタートアップ「Manus」が7500万ドル(約115億円)の資金調達に成功した。同社は産業用ロボット向けAIソフトウェアを開発しており、特に製造業における複雑な作業の自動化技術に強みを持つ。
今回の資金調達はSequoia China主導で行われ、既存投資家のTencent Venturesも参加した。調達資金は研究開発の加速と国際展開に充てられる予定で、特に日本と東南アジア市場への進出を計画している。中国政府の製造業高度化政策「中国製造2025」の追い風もあり、今後の成長が期待されている。
20. AIエージェント管理が必須スキルに
Microsoftが発表した「Work Trend Index 2025」によると、AIエージェントの管理能力が今後のビジネスパーソンに必須のスキルになると予測されている。
調査対象の経営者の78%が「AIエージェント管理能力」を今後3年以内に重要なスキルと位置づけており、すでに31%の企業が採用基準に取り入れている。AIエージェント管理とは、複数のAIツールを効果的に連携させ、業務フローを最適化する能力を指す。
Microsoftはこの傾向を受け、AIエージェント管理に特化した教育プログラムを開発中であり、2025年中に提供開始を予定している。
日本の教育に活かせるAIの可能性は?
AI技術の進化は、日本の教育や学習塾に多くの革新をもたらす可能性があります。
まず、OpenAIのChatGPTディープリサーチ軽量版やPerplexityの音声AIアシスタントは、個別最適化された学習支援や質問対応を自動化できるため、生徒一人ひとりの理解度や進度に合わせた指導が実現しやすくなります。
また、Gamma 2.0やAdobe Fireflyのような生成AIによるプレゼンテーションや画像・動画生成機能は、探究学習や創造的な課題活動に活用でき、児童生徒の表現力や主体性を伸ばす教材作成にも役立ちます。
さらに、AIによる学習履歴の分析や苦手分野の抽出、最適な教材提示といった機能は、塾や学校での個別指導の質を高め、教師の負担軽減や業務効率化にも寄与します。
文部科学省も校務や授業でのAI活用を推進し、ガイドラインを整備しています。
今後はさらに、AIを「正しく怖れ、前向きに活用」し、学びの質向上と持続的な教育環境の構築を目指すことが重要になるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
