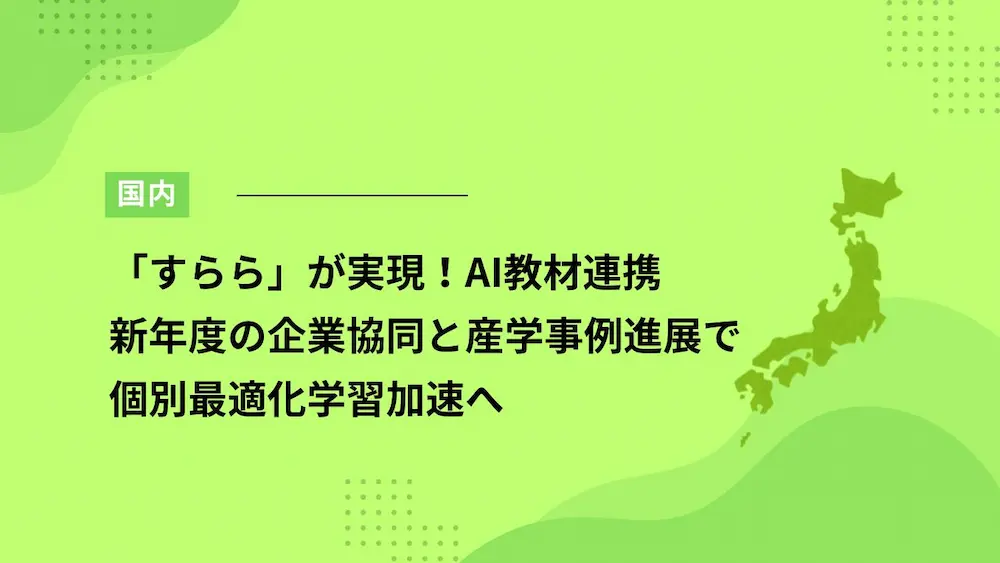
教育現場でのAI活用が加速している。
すららネットの「すららドリル」とコニカミノルタの「tomoLinks」が国内初となるAIドリル同士の連携を発表し、また「すららドリル」は埼玉県ふじみ野市における小学校への大規模導入も始まった。
「つまずき分析」と「学習定着度分析」を組み合わせた新しい学習支援の仕組みは、児童生徒一人ひとりに最適化された学びをどう変えていくのか。
教育DXの最前線から、未来の教室の姿を探っていく。
【記事の要約】
すららネット株式会社の「すららドリル」と連携し、コニカミノルタジャパン株式会社は、学校教育向けソリューション「tomoLinks(トモリンクス)」の「先生×AIアシスト」サービスにおいて、2025年度中に両社のAIを組み合わせた新しい学習支援の仕組みを開始する。
この連携は、初等中等教育における公教育市場において、AIを搭載したデジタルドリル同士の連携としては国内初となる取り組みである。
「tomoLinks」の「先生×AIアシスト」サービスのAIは、全国学力・学習状況調査や他社のデジタルドリルといった外部データをもとにした「包括的な学習定着度の分析」を得意とする一方、「すららドリル」のAIは解けない原因を自動的に判断し、必要な問題を適切に提示する「つまずき分析」に優れている。
両者の連携により、児童生徒はやみくもに問題数をこなすことなく、自分のつまずきを可視化し、確実に克服しながら学習を進められる仕組みが実現する。
他方、埼玉県ふじみ野市では、2024年から市内中学校に導入されていた「すららドリル」が、2025年4月から市立小学校12校の小学4~6年生約3,000人にも拡大導入された。
「すららドリル」は、AIが学習履歴をもとに最適な問題を出題し、基礎からスモールステップで学力を定着させるため、日常的な学びの質を高める教材として期待されている。
約20万問の豊富な問題群や弱点診断、アニメーションレクチャー、自動採点機能により、児童は「できた」「わかった」という実感を積み重ねながら自信を育み、主体的・自律的な学習習慣の定着も期待できる。
(出典元:2025年4月21日・22日 PR TIMESより)
今後の学校教育への活用と可能性は?
これらのAI教材の連携と導入拡大は、今後の学校教育に大きな変革をもたらす可能性があります。
まず、個別最適な学びの実現という点で、児童生徒一人ひとりの学習ペースや理解度に合わせた教材提供が可能になります。
特に「tomoLinks」と「すららドリル」の連携によって、学習定着度の分析とつまずき分析が組み合わさることで、より精緻な学習支援が実現できるでしょう。
また、教員の業務負担軽減という観点からも、課題配信や採点業務の自動化、進捗状況の可視化といった機能によって、教員が児童生徒と向き合う時間を確保できるようになります。
さらに、教育データの活用により、教育委員会による自治体全体の教育改善や教育政策立案にも役立てることができ、教育現場の課題解決を支援することにもつながります。
将来的には、こうしたAI教材の連携がさらに進み、不登校や外国籍の児童、発達障がいを持つ子どもたちなど、多様な学習者に対しても適切な学習機会を提供できるようになるでしょう。
教育DXの加速により、誰一人取り残すことのない教育環境の構築が期待されます。
