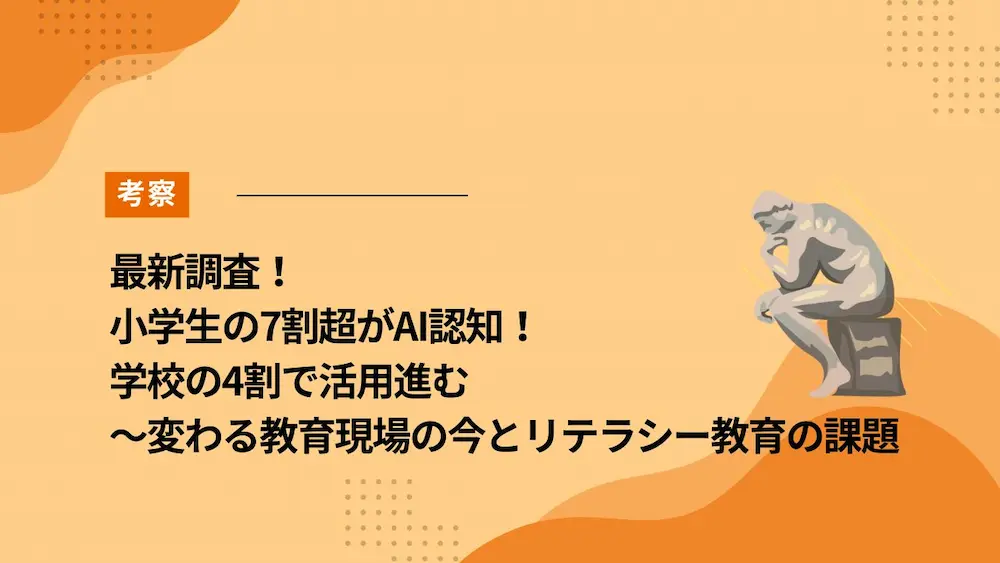
ベネッセ社の最新調査によれば、小学生の生成AI認知率は74.7%に達し、3年前から約26ポイント上昇しました。
学校現場でも約4割の児童が授業や宿題でAIを活用した経験があり、教育現場でのAI導入が急速に進んでいます。
一方で、AIの誤りに気づいた児童も約6割おり、情報収集力向上と思考力低下という二面性が浮き彫りになっています。
生成AIが「当たり前」になりつつある今、学校はどのように対応し、子どもたちにどんなリテラシー教育を提供すべきなのでしょうか。
記事の要約
株式会社ベネッセコーポレーション(岡山県岡山市)は、小学3年生から6年生とその保護者1,032組を対象に、生成AIに関する意識調査を行った。
2023年から2025年の比較で、小学生の生成AI認知率は47.8%から74.7%へと大幅に上昇し、保護者も89.6%に達した。
AI利用経験のある小学生は80%超となり、習慣化している。
家庭では親のデバイスを子どもが使うケースが最多で、自分専用デバイスの利用も増加傾向にあるが、親が子の代わりに調べる割合は2割弱にとどまる。
生成AIを巡る家庭内での対話は約5割で、2023年から大きな変化は見られない。
保護者はAI利用による「情報収集力の向上」「思考力の発展」などのポジティブな側面と、「自分で考える機会の減少」といったネガティブな側面の双方を認識している。
他には、約4割の小学生が学校の授業・宿題でAIを利用した経験があり、AI活用が一定程度進展している。
(出典元:2025年11月21日 PR TIMES・株式会社ベネッセコーポレーションより)
教育現場での生かし方と今後は?
生成AIは小学生にも広く認知され、利用経験が習慣化し始めています。
今後の学校教育では、生成AIを単なる便利な道具として活用するだけでなく、情報リテラシー教育や自己主導的な学習を支える仕組みとして取り入れることが重要だと考えます。
調査結果では保護者が「情報収集力の向上」や「考える力の発展」に期待する一方、「自分で考える機会の減少」を懸念していることが分かりました。
そのため、児童にAIの使い方だけでなく、AIとの距離感やAIの限界・誤りの見抜き方を教えるカリキュラムが求められます。
現在、学校の4割で授業や宿題へのAI活用経験があることからも、今後さらに教育の現場で活用が進むと予想されます。
生成AIの普及に伴い、「人間ならではの力」を育てる新たな教育アプローチと、家庭・学校が連携してリテラシーや倫理観を養う資質・能力開発がますます必要になります。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001417.000000120.html
