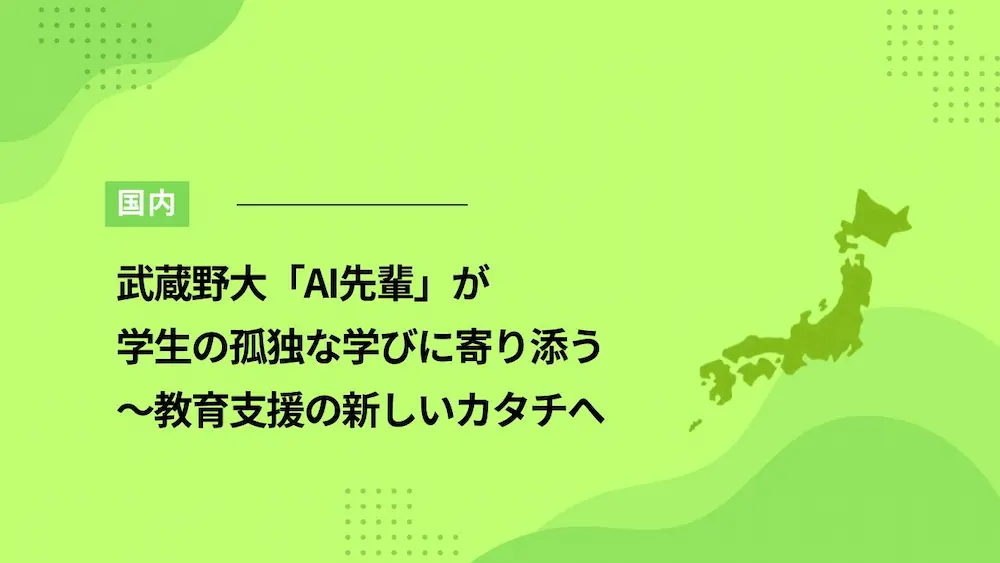
通信教育の孤独感を解消する、生成AIを活用した国内初という試みが始まりました。
武蔵野大学が今年10月から導入した「AI先輩」は、教科書準拠型のGPTsで、学生の質問に24時間対応します。
「わからないことを気軽に聞ける先輩」として設計されたこのシステムは、個別最適化された学びを実現し、教育現場の課題解決に新たな道筋を示しています。
小・中・高校での応用可能性も含め、AI時代の教育支援の最前線の一例となりそうです。
記事の要約
武蔵野大学(東京都江東区)は2025年10月より、通信教育部心理学専攻の学生向けに国内初のGPTsベース学修支援サービス「AI先輩」を開始した。
このシステムは教科書や講義内容を学習し、学生の質問に教材に基づいて回答するほか、記載のない内容は自らの考えとして補足する機能を持つ。
通信教育特有の孤独感や質問しにくさという課題に対し、「先生の代替ではなく親切な先輩」として学生に寄り添う設計となっている。
先行トライアルでは「難しい定義がわかりやすく整理される」「つまずきを軽減できる」「興味の深掘りや図書提案で学びが広がる」といった評価が得られた。
対象科目は「心理学概論」「心と体の健康」「行動療法」の3科目で、計2,000名超の受講者を擁する。
(出典元:2025年10月14日 PR TIMES・学校法人武蔵野大学より)
学校教育への応用と可能性は?
この「AI先輩」の取り組みは、小学校から高校までの学校教育にも多様な可能性をもたらすでしょう。
特に個別最適化された学びの実現において、授業後や家庭学習で気軽に質問できる環境を提供することで、教師への質問をためらう生徒や理解度に差がある生徒への支援が期待できます。
また、教科書準拠型AIは基礎学力の定着を促進し、発展的な学習への興味喚起にも寄与するでしょう。
不登校や病気療養中の児童生徒にとっては、孤立感を軽減しながら継続的な学習機会を確保する手段となり得ます。
将来的には各教科に特化したAIアシスタントの開発や、生徒の学習履歴を分析した個別カリキュラムの提案など、教員の働き方改革と教育の質向上を両立させる基盤技術として発展する可能性があります。
情報元はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000308.000067788.html
