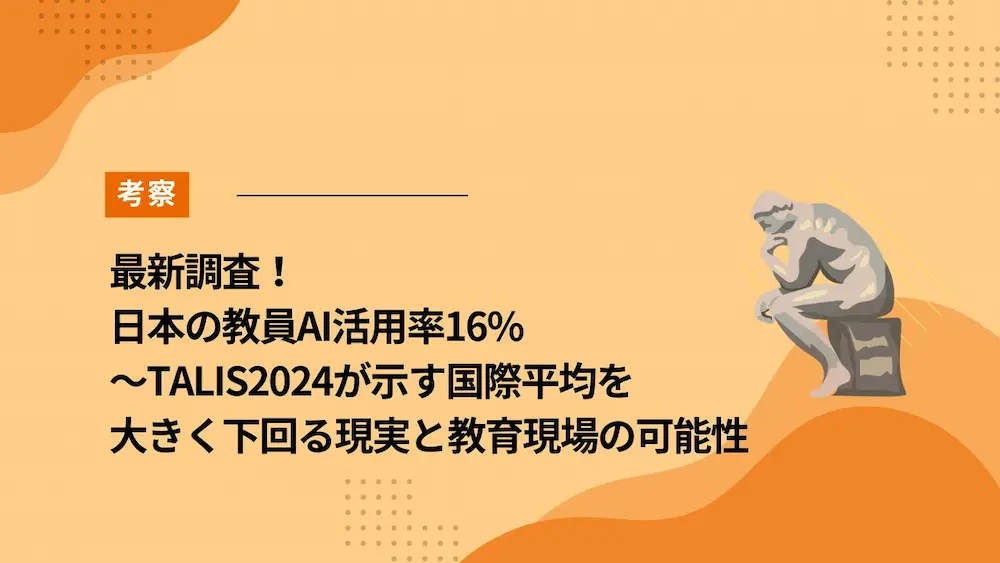
今年10月に公表された、学校の学習環境と教員の勤務環境に焦点を当てたOECD(経済協力開発機構)の国際調査である国際教員指導環境調査TALIS2024の最新結果から、日本の教育現場における実態が明らかになりました。
授業でAIを活用する教員はわずか16~17%と国際平均の半分以下である一方、個別サポートや事務業務効率化への期待は国際平均を大きく上回っています。
参加国中で最長の仕事時間に悩む日本の教員にとって、本当にAIは働き方改革の切り札となり得るのでしょうか。
資料の要約
TALIS2024調査によると、日本の教員におけるAI活用状況は国際平均を大きく下回っている。
過去12か月間に授業でAIを使用した教員の割合は、小学校で16.0%、中学校で17.4%と、参加国平均(小学校36.9%、中学校36.3%)の半分以下に留まった。
一方で、日本の教員はAIの教育的有用性を高く評価しており、授業計画の作成改善(小学校55.7%)、教材の個別調整(小学校64.8%)、個別サポートの支援(小学校71.1%)、事務業務の自動化(小学校79.1%)などの項目で、いずれも国際平均を上回る肯定的評価を示している。
しかし同時に、AIが児童生徒の偏った見方を増大させるリスク(小学校48.4%)や、不適切な提案をする可能性(小学校67.0%)など、AIに関するリスクを認識している教員の割合も国際平均より高く、日本の教員は慎重な姿勢を示している。
なお、次回調査は2030年に実施予定。
(出典元:2025年10月7日 OECD公表・国立教育政策研究所より)
今後の学校教育への示唆は?
今後の学校教育では、AIの活用促進と教員研修の充実が重要な課題です。
現状では日本の教員のAI使用率は低いものの、その教育的価値への理解は高く、特に個別最適な学びの実現や教員の業務負担軽減という観点で大きな可能性を秘めています。
文科省が推進する「個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実」の実現において、AIは児童生徒の能力に応じた教材調整や個別サポートを効率的に支援するツールとして活用できます。
一方で、日本の教員が指摘するAIのリスク認識は重要な視点であり、批判的思考力の育成や情報リテラシー教育を並行して進める必要があるのではないでしょうか。
教員の仕事時間が参加国中で最長という現状を踏まえると、AIによる事務業務の自動化は働き方改革の推進にも寄与する可能性があり、教員がより質の高い指導に専念できる環境づくりに貢献することが期待されるでしょう。
情報元はこちらからご覧ください。
・国立教育政策研究所
https://www.nier.go.jp/kokusai/talis/index.html
・文部科学省
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/data/Others/1349189.htm
