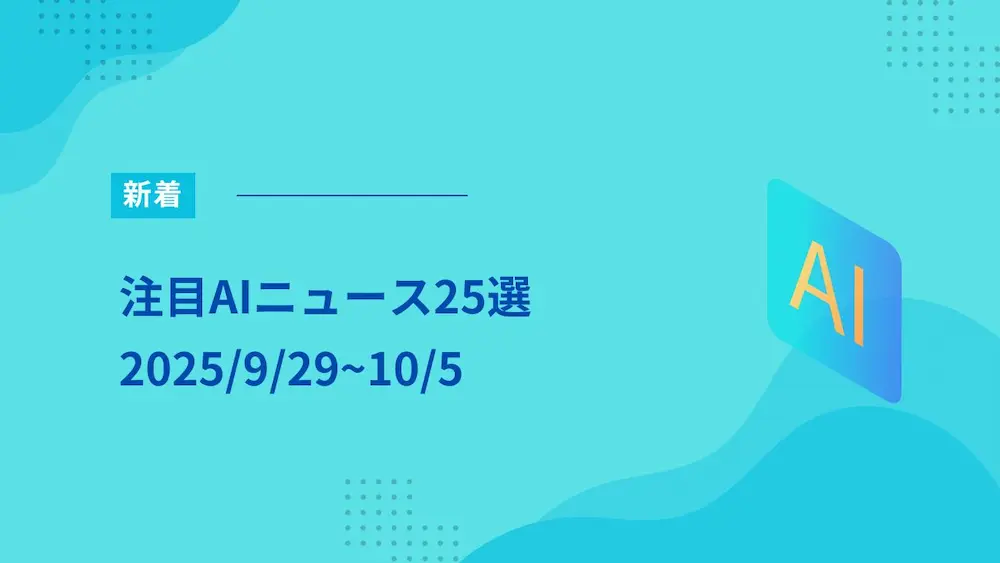
最新の生成AIニュース(2025年9月29日~10月5日)を、YouTubeチャンネル「いけともch」の池田朋弘氏が注目した25のキーワードで紹介します。
1. OpenAIが映像生成モデル「Sora 2」発表
OpenAIが最新の映像生成モデル「Sora 2」を発表した。
最大の特徴はカメオ機能で、ユーザーが1分間顔を認証すると、自分や許可した他者の映像を高精度で生成できる。新SNS「Sora」も同時公開され、TikTok風のインターフェースで動画を共有可能だ。
2. ChatGPTビジネスに「共有プロジェクト」追加
ChatGPTのビジネスプランに共有プロジェクト機能が追加された。
チームメンバー間でプロジェクトを共有し、同じ資料や事前指示を使って協働作業が可能になる。プロジェクト専用のメモリー機能により、チーム全体で一貫した文脈を保ちながらAIを活用できる。
3. ChatGPTに「安全ルーティング」「ペアレンタルコントロール」導入
ChatGPTに未成年保護のための新機能が実装された。
ペアレンタルコントロールにより、保護者が子供の利用時間制限や画像生成の可否を設定できる。問題のある相談内容があった場合は保護者に通知される仕組みで、より安全な利用環境を提供する。
4. MicrosoftがCopilotに「Agent Mode」「Office Agent」導入
MicrosoftがCopilotに2つの重要機能を追加した。
Agent ModeはExcelやWordで複雑なデータ分析を自動実行し、関数も正確に生成する。Office Agentは、GammaやGensparkのような高品質なプレゼンテーション資料を社内データを使って作成できる実用的なツールである。
5. Anthropicが新モデル「Claude Sonnet 4.5」公開
Anthropicが最新モデル「Claude Sonnet 4.5」を発表した。
コーディング能力が大幅に向上し、最大30時間の連続処理が可能になった。GPT-4やGemini 2.5 Proを上回るベンチマーク結果を示し、特にソフトウェア開発分野での性能向上が著しい。
6. AnthropicがClaude Codeを強化アップデート
Claude Codeが大幅に機能強化された。
Claude 4.5ベースとなり精度が向上したほか、チェックポインティング機能で作業の自動保存が可能になった。CursorやVS Code向けの専用拡張機能も追加され、エンジニアでなくても言葉でソフトウェア開発ができる環境が整った。
7. Claude for Chromeが徐々に公開
Anthropicがブラウザ拡張機能「Claude for Chrome」の提供を開始した。
Webページを閲覧しながら右側のパネルでClaudeに相談でき、ページ内容を分析してスプレッドシートにまとめるなどの自動操作が可能だ。定型処理はショートカット化して効率的に実行できる。
8. GoogleがスライドとVidsに画像生成AI「Nano Banana」導入
Googleが「Google スライド」と「Google Vids」に最新の画像編集AIモデル「Nano Banana」を実装した。
画像内の特定部分を編集したり、カスタムプロンプトで背景変更などの細かい調整が可能になった。スライド上で直接画像を編集できるため、デザインツールを開く手間が不要である。
9. PerplexityがAIブラウザ「Comet」を全ユーザー向けに無料化
Perplexityが提供するAIブラウザ「Comet」が無料開放された。ブラウジング中にいつでもPerplexityに質問でき、検索結果を即座に表示する。
ページの自動操作機能も搭載し、管理画面で特定の情報を探す際などに活用できる。月200ドルのMAXプラン限定だった機能が誰でも使用可能になった。
10. Canva AIが日本語を含む16言語に対応
デザインツール「Canva」のAI機能が日本語を含む16言語に対応した。
会話形式でデザインを依頼すると、写真を使ったバナーやSNS投稿用の画像を自動生成する。完璧ではないものの、言葉でデザインツールを操作できる環境が整い、専門知識がなくてもデザイン制作が可能になった。
11. Sunoがショート動画のHookを公開
音楽生成AI「Suno」がショート動画SNS機能「Hook」を発表した。
Sunoで作成した音楽を使った短尺動画を作成・共有できるプラットフォームで、TikTok風のインターフェースを採用している。ユーザーは音楽を選び、それに合わせた映像を追加することで、音楽主体のショート動画を簡単に制作できる。
12. Dream machineが新たなモデル「Ray3」をリリース
Lumaの動画生成サービス「Dream Machine」が新モデル「Ray3」を公開した。
映画レベルの高品質な映像生成が可能で、アノテーション機能により特定の人物や物体の動きを細かく指定できる。推論技術を活用することで再現性と現実感が向上し、段階的に考えながら高品質な動画を生成する。
13. GMOグループで生成AI活用率が95%に到達
GMOインターネットグループの2025年9月の調査で、生成AI業務活用率が95.0%に達した。
活用する従業員の73.6%が「ほぼ毎日」使用し、月間約25.1万時間の業務削減を実現している。これは1,572人分の労働力に相当し、複数AIサービス利用率も80%に達した。
14. Inception Point AIがAIポッドキャスト量産
Inception Point AIがAIを活用したポッドキャスト量産システムを開発した。
複数のAIツールを組み合わせることで、効率的にポッドキャストコンテンツを大量生成できる仕組みを構築している。音声生成技術の進化により、従来は時間がかかっていたポッドキャスト制作が大幅に効率化される可能性がある。
15. OpenAIがChatGPTに「Instant Checkout」導入
OpenAIがChatGPT内で商品を直接購入できる「Instant Checkout」機能を実装した。
EtsyやShopifyと提携し、ChatGPTでの会話中に商品を見つけたら、そのまま購入手続きが可能になる。会話型AIが単なる情報提供ツールから、実際の商取引プラットフォームへと進化している。
16. OpenAIがChatGPT向け広告基盤の構築を開始
OpenAIがChatGPTに広告を表示するためのマーケティングプラットフォーム構築を開始した。
求人情報から広告関連の職種募集が明らかになり、ChatGPTの収益化戦略の一環として広告事業への参入が進んでいる。無料ユーザー向けの収益源確保と、サービス持続可能性向上が目的とされる。
17. OperaがAI搭載ブラウザ「Neon」を月額制で発表
Operaが新しいAI搭載ブラウザ「Neon」を月額課金モデルで発表した。
ブラウジング体験全体にAI機能を統合し、より高度な自動化や情報処理を提供する。従来の無料ブラウザとは異なり、サブスクリプション型のプレミアムAIブラウザという新しいビジネスモデルを展開している。
18. Thinking Machines Labが新ツール「Tinker」発表
Thinking Machines LabがAIモデルを簡単にファインチューニングできる新ツール「Tinker」を公開した。
専門知識がなくても、独自のデータセットを使ってAIモデルをカスタマイズできる。企業が自社特有のニーズに合わせてAIモデルを調整し、より実用的なAIシステムを構築できる環境が整いつつある。
19. OpenAI「DevDay 2025」の注目ポイント
OpenAIが2025年10月6日にサンフランシスコで開催する開発者向けイベント「DevDay 2025」が注目されている。
過去最大規模で1,500人超の開発者が集結し、次世代モデルや新ツールの初公開が予定されている。GPT-5の詳細発表や新しいAPIの紹介が期待される。
20. サム・アルトマンがSoraの改善方針と収益化計画を発表
OpenAIのCEOサム・アルトマンが、ブログでSoraの今後の方向性を公表した。
動画生成品質の改善と処理速度の向上を優先課題とし、ユーザーフィードバックを積極的に反映する方針を示した。また、Soraの収益化計画についても言及し、持続可能なサービス提供体制の構築を目指している。
21. OpenAIが資産管理アプリ「Roi」を買収
OpenAIが個人向け資産管理アプリケーション「Roi」を買収した。
AIを活用した金融サービス分野への進出を本格化させる動きとみられる。Roiの分析機能とパーソナライゼーション技術を統合することで、ChatGPTに金融アドバイス機能を追加する可能性が高い。
22. OpenAIとデジタル庁が生成AI活用で戦略的協力を開始
OpenAIと日本のデジタル庁が生成AI活用における戦略的協力関係を締結した。
行政サービスへのAI導入促進や、安全なAI利用環境の整備に向けて連携する。公共部門でのChatGPT活用事例の創出と、日本語対応の強化が期待される協力体制である。
23. Sora 2が生成したアニメ風動画に著作権上の懸念が拡大
Sora 2で生成されたアニメ風動画が既存作品に酷似しているとして、著作権侵害の懸念が広がっている。
特定のアニメキャラクターやスタイルを模倣した動画が生成可能なため、知的財産権保護の観点から問題視されている。AI生成コンテンツの権利関係をめぐる議論が活発化している。
24. NICT・PFN・さくらインターネットの3社が国産生成AIで連携
情報通信研究機構(NICT)、Preferred Networks(PFN)、さくらインターネットの3社が国産生成AI開発で連携を発表した。
日本独自の技術基盤とデータセンターを活用し、国内でのAI主権確立を目指す。海外製AIへの依存を減らし、日本語に最適化された高性能モデルの開発を推進する。
25. 生成AIの普及で「ワークスロップ」が増加
生成AIの普及に伴い、業務効率が低下する「ワークスロップ」現象が増加している。
AIツールの使い方を学ぶための時間や、生成結果の確認・修正作業が増え、かえって業務時間が延びるケースが報告されている。適切な活用方法の習得と、業務プロセスの再設計が課題となっている。
今後の日本の教育において注目の技術は?
まず、MicrosoftのCopilot「Agent Mode」とChatGPTの「共有プロジェクト」機能です。
Agent Modeでは、ExcelやWordで複雑なデータ分析を言葉で依頼するだけで、関数を正確に生成し、相関関係の分析やグラフ作成まで自動で行います。
これにより、学習塾での成績管理や生徒データの分析が劇的に効率化され、データに基づく個別指導計画の作成が容易になります。
教員がExcelに詳しくなくても、「成績が伸びた生徒の特徴を分析して」と依頼すれば、AIが自動処理してくれるのです。
また、ChatGPTの共有プロジェクト機能は、チーム内で同じ資料や指示を共有しながら協働作業ができるため、学年担当教員や塾の講師チームが一貫した教育方針のもと、効率的に教材開発や指導案作成を進められます。
さらに、Claude 4.5やGoogle SlidesのNano Bananaなど、画像編集やプレゼン資料作成を支援するツールも充実しており、教材作成の時間を大幅に削減できます。
これらのツールを活用することで、教員は本来の「教える」時間を確保し、生徒一人ひとりに向き合う質の高い教育が実現できるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
