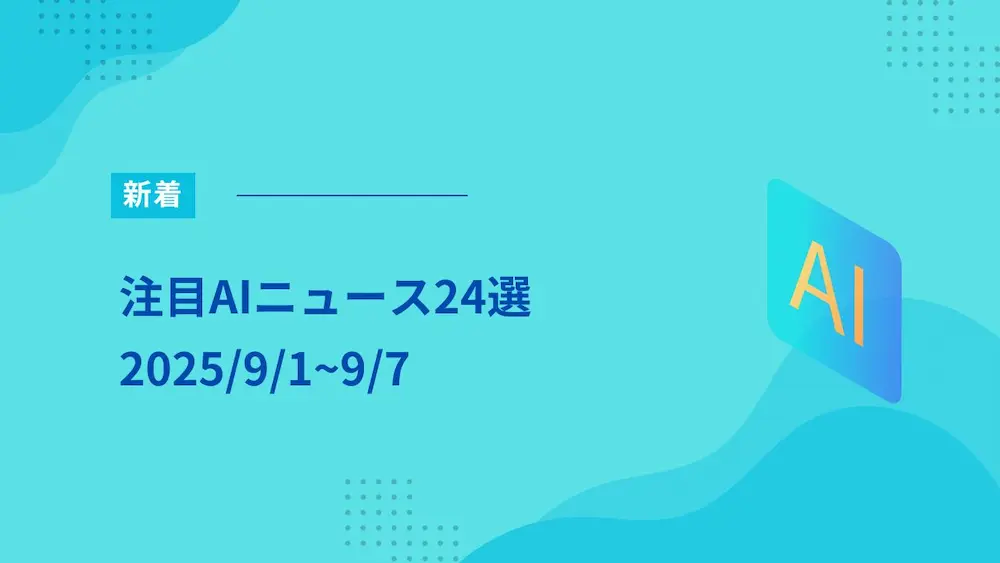
最新の生成AIニュース(2025年9月1日~9月7日)を、YouTubeチャンネル「いけともch」の池田朋弘氏が注目した24のキーワードで紹介します。
1. ChatGPTのプロジェクト機能~無料版ユーザーも利用可能に
ChatGPTの無料版でプロジェクト機能が利用できるようになった。
この機能により、特定のテーマごとにチャットを整理し、プロジェクト内で話した内容をAIが記憶する。無料版では5個、有料版では25個以上のファイルをプロジェクトに追加可能。
2. ChatGPTで会話の分岐機能が追加
ChatGPTで長い会話の途中から別の方向性で議論を続けられる分岐機能が追加された。
過去の任意の時点に遡って新しいチャットを作成でき、それまでの文脈は保持される。プロジェクト機能と組み合わせることで、より効率的な会話整理が可能になった。
3. NotebookLMにAudio Overviewトーンカスタマイズ機能追加
NotebookLMの音声解説機能に3つの新パターンが追加された。
概要(2分程度の短縮版)、評論(専門家による改善提案)、議論(対立する2つの立場での討論)から選択可能。従来の詳細な議論と合わせて4パターンで、多角的な内容理解が効率化される。
4. GensparkがAI動画編集Clip Genius
GensparkがClip Geniusという動画自動編集サービスを提供開始。
YouTubeなどの動画URLを入力すると、AIが内容を分析して重要な部分を自動で切り抜く。1時間50分の動画から特定テーマの部分のみを抽出するなど、効率的な動画編集が可能である。
5. AIのデザイン能力を評価する「Design Arena」
AIモデルのデザイン能力を比較評価するプラットフォーム「Design Arena」が登場。
ユーザーが複数のAI生成デザインを投票で評価し、ランキングを作成。現在はClaude Opusが最高評価を獲得している。ウェブサイト、ゲーム、3Dなどカテゴリー別の評価も可能である。
6. サイバーエージェント「AIクリエイティブBPO」の生成AIで制作改革
サイバーエージェントがAIクリエイティブBPOサービスを展開。
専用AIツールと人材体制により、1人当たり月30本から220本、トップクリエイターは700本の制作を実現。ベネッセなどの事例で成果を上げ、300人体制のスタジオで各業界に展開している。
7. アクセンチュアの最新生成AI活用戦略
アクセンチュアは社内AIプラットフォームに300以上のAIアプリを展開し、AIレビュー、データ分析、プレゼンテーション自動生成など幅広く活用している。
14パターンのプレゼンテーション形式で高品質資料を自動作成し、社内データと連携した強力なAI活用体制を構築している。
8. クレディセゾンがAIワーカー化による全社変革戦略「CSAX」を発表
クレディセゾンがChatGPTエンタープライズを全社4000名に導入し、AIワーカー化を推進している。
実証実験では1人当たり月14時間の削減を達成し、営業資料作成、管理業務、研修動画作成等で成果を上げ、全社的なAI活用戦略を展開している。
9. ニーリーがAIでコールセンター通話要約を自動化
コールセンター運営会社ニーリーがAmazonの仕組みとClaude3.5を活用し、電話終了から10秒以内で高度な通話要約を自動生成するシステムを構築した。
月数万件を処理し、高精度かつ高速な要約システムを実現している。
10. Kongの企業におけるLLM導入状況レポート
API管理プラットフォーム企業Kongが実施した調査によると、企業内AI利用ではGeminiのシェアが69%でOpenAIを逆転した。
GoogleWorkspaceとの統合効果が大きく、企業向けAI市場での競争が激化している状況が明らかになった。
11. Google PhotosにVeo3での動画化が追加
Google PhotosにVeo3を使った写真から動画生成機能が追加された(米国版のみ)。
撮影した写真を簡単に4秒程度の高品質動画に変換でき、音声なしながら非常に自然な映像を生成する。現在はコストの関係で利用回数制限がある模様である。
12. Amazonショッピングアプリの新機能「Lens Live」
AmazonアプリのLens機能が強化され、動画から商品を認識してAIアシスタントRufusと連携する機能が追加された。
映っている商品の詳細情報を瞬時に取得し、価格や仕様をAIに質問できる新しいショッピング体験を提供している。
13. BraveがPerplexityのAIブラウザCometの脆弱性を警告
BraveがPerplexityの AIブラウザ「Comet」に深刻な間接的プロンプトインジェクション脆弱性を発見した。
Webページの隠れた悪意ある指示をAIが処理し、他のタブの個人情報にアクセスして攻撃者に送信する危険性がある。Perplexityは修正したと発表したが、Braveは不完全として再報告している。
14. Microsoftの1.5Bパラメータ音声モデル「Vibe Voice 1.5B」
Microsoftが15億パラメータの音声合成モデル「Vibe Voice 1.5B」を発表した。
高品質な音声合成が可能で、ポッドキャストやナレーション等の音声コンテンツ自動生成に活用できる。MITライセンスで提供され、研究・商用利用の両方に対応している新世代の音声AI技術である。
15. OpenAIがAI採用プラットフォーム「OpenAI Jobs Platform」発表
OpenAIがAIによって職を失う可能性のある人材向けの就職支援プラットフォーム「OpenAI Jobs Platform」の開発を進めている。
AIの普及で影響を受ける労働者の転職支援を目的とし、AI時代の雇用問題に対するOpenAI独自のアプローチを示している。
16. OpenAIが製品テスト企業Statsigを約11億ドルで買収
OpenAIが製品テスト・実験プラットフォーム企業Statsigを約11億ドルで買収した。
Statsigの技術により、AIモデルのA/Bテストや性能評価を強化し、製品開発プロセスの最適化を図る。OpenAIの事業拡大と技術強化を目的とした戦略的買収である。
17. OpenAIが会話監視と警察通報の可能性を認める
OpenAIが特定の状況下でユーザーの会話を監視し、必要に応じて警察当局に通報する可能性があることを認めた。
自殺予防や重大犯罪防止を目的とするが、プライバシーと安全性のバランスを巡って議論を呼んでいる。AI企業の責任範囲に関する重要な論点となっている。
18. Googleの新AI画像編集「Nano Banana」が話題に
GoogleがピクセルスマートフォンシリーズにAI画像編集機能「Magic Eraser」の進化版として「Nano Banana」を導入した。
写真から不要なオブジェクトを自然に除去し、背景を自動補完する機能が大幅に向上。スマートフォンでの高度なAI画像編集が一般化している。
19. Anthropicが著作権訴訟で15億ドル規模の和解に合意
AnthropicがClaudeの学習に海賊版書籍を無断使用した著作権侵害訴訟で、史上最大となる15億ドル(約2200億円)の和解に合意した。
約50万作品を対象に、作品1点あたり3000ドルが支払われ、海賊版データの完全削除も義務付けられた。AI企業の著作権責任を明確化した重要な先例となった。
20. Anthropicが中国などへのAIサービス提供を停止
Anthropicが国家安全保障上の懸念から、中国、香港、その他複数国への AIサービス提供を停止した。
米国政府の対中技術規制強化に対応した措置で、地政学的緊張がAIサービスのグローバル展開に影響を与えている。他のAI企業も同様の措置を検討している状況である。
21. The Browser Company が買収~生成AIブラウザー競争が加速
「Arc」ブラウザで知られるThe Browser Companyが買収され、生成AIブラウザー開発競争が激化している。
PerplexityのCometやBraveの取り組みと合わせ、従来の検索中心ブラウザからAI対話型ブラウザへのシフトが加速。ブラウザ業界の構造変化が進んでいる。
22. AI雇用影響~若年層に限定的減少
最新の研究により、AI導入による雇用への影響は従来予測より限定的で、特に若年層の雇用減少は軽微であることが判明した。
AI技術の導入により新たな職種が創出される一方、既存業務の効率化により一部職種は影響を受けるが、全体的な雇用への破壊的影響は当初懸念より小さいとされている。
23. ChatGPTを心理的説得で操作可能とする研究結果
研究者がChatGPTの安全フィルターを心理的説得技術により回避できることを実証した。
共感的な言葉遣いや権威性の主張などの手法により、本来制限されるべき有害なコンテンツの生成を可能にする脆弱性が発見された。AI安全性システムの改善が急務とされている。
24. MIT研究~ChatGPT依存で脳機能と記憶力が低下
MITの研究により、ChatGPTなどのAIアシスタントに依存したエッセイ作成を行うと、長期的に脳の神経活動が低下し、記憶力や認知能力に悪影響を与える可能性が明らかになった。
AI利用による認知的依存が脳機能の退化を招く懸念があり、適切なAI活用方法の検討が必要とされている。
日本の教育現場で活用が期待できるのは?
まずは、NotebookLMの音声機能です。
学習資料を登録するだけで、概要、評論、議論の3つのパターンで音声解説を生成できるため、生徒の理解レベルに応じた多角的な学習が可能になります。
通学時間や復習時に「聞く学習」として取り入れることで、学習効率を大幅に向上させられるでしょう。
次に、ChatGPTのプロジェクト機能と会話分岐機能も教育現場で有効です。
科目ごとにプロジェクトを作成し、学習履歴を蓄積することで、個別指導の質を高められます。
会話分岐機能により、同じ問題でも複数の解法を並行して検討でき、生徒の思考力育成に役立ちます。
ただし、MIT研究が示すようにAI依存による脳機能低下のリスクも指摘されています。
教育現場では、AIを思考の補完ツールとして位置付け、生徒自身の考える力を育てることとのバランスが重要です。
塾や学校では、AIの効率性を活用しながらも、批判的思考や創造性を伸ばす指導方針を確立する必要があるでしょう。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
