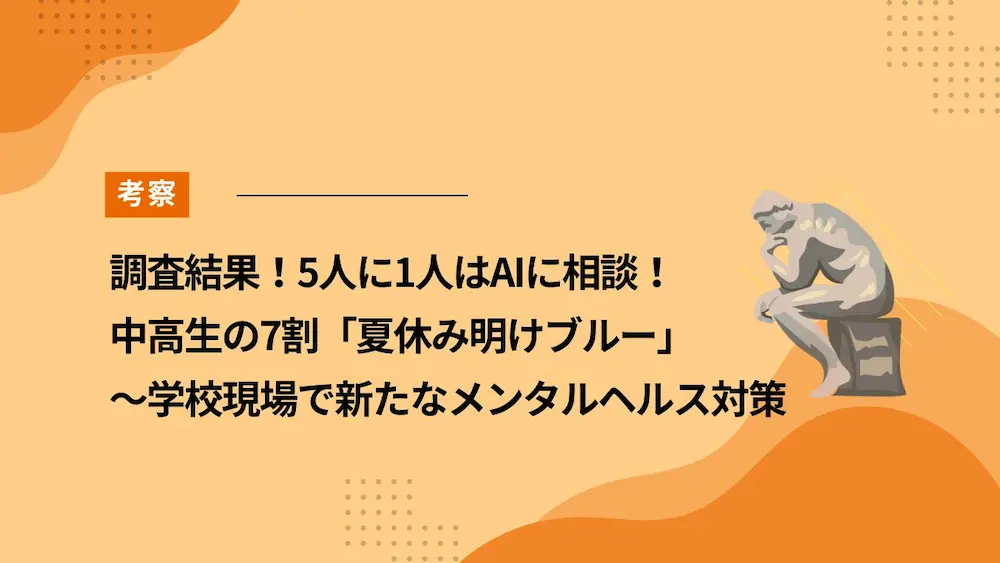
最新調査によると、夏休み明けの憂うつな気持ちを抱える中高生が約7割に上ることが明らかになりました。
この「夏休み明けブルー」の背景には生活リズムの乱れや友人関係への不安があり、従来の相談相手である友人や家族に加え、なんと5人に1人の生徒がAIを相談相手として活用している実態が浮き彫りになったのです。
学校教育現場では、生徒の心の健康をどのようにサポートすべきなのでしょうか。
注目されるのは、感情を書き出すジャーナリングという手法です。
認知度はわずか4.3%ながら、実践した生徒の約8割が効果を実感しており、教育現場での活用可能性が大きく期待されています。
【記事の要約】
feppiness株式会社(福岡県糸島市)が全国の中高生416名を対象に実施した調査により、中高生の心理状況の深刻な実態が明らかになった。
調査結果によると、約7割の中高生が夏休み明けの「学校に行きたくない・気が重い」という憂うつな感情を経験しており、主な原因として「朝起きられない」(43.3%)、「生活リズムの乱れ」(35.8%)、「友達関係への不安」(28.4%)が上位を占めている。
また、普段からモヤモヤやストレスを感じる中高生も約7割に達し、具体的な要因は「友人・クラスの人間関係」(49.9%)、「勉強や成績」(47.2%)、「将来への不安」(40.2%)となっている。
特筆すべきは、5人に1人(21.0%)がAIを相談相手として活用している点である。
一方、ジャーナリング(思考や感情を書き出す行為)の認知度は4.3%と低いものの、実践者の約8割が心の整理や自己理解に効果を実感している。
(出典元:2025年9月3日 PR TIMES、同3日 こどもとITより)
学校教育への活用と将来の可能性は?
この調査結果は、現代の学校教育に重要な示唆を与えています。
まず、中高生の7割がストレスを抱えている現状を受け、学校には従来の学習指導に加えて、生徒の心の健康をサポートする仕組みが必要です。
具体的には、ジャーナリングのような自己理解を深める手法を授業や部活動に導入することで、生徒が自分の感情を整理し、自己肯定感を高められる環境を提供できるでしょう。
また、AIが相談相手として受け入れられている実態は、教育現場にデジタル技術を活用した新しいカウンセリング手法の可能性を示しています。
将来的には、AI技術とジャーナリングを組み合わせた個別化されたメンタルヘルスケアシステムの構築が期待されます。
これにより、生徒一人ひとりの心理状況を適切に把握し、早期の支援介入が可能となるでしょう。
さらに、科学的根拠のあるエクスプレッシブ・ライティングの手法を教育カリキュラムに組み込むことで、生徒の心理的柔軟性と自己理解能力を系統的に育成できると考えられます。
情報元の内容はこちらからご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000099124.html
https://edu.watch.impress.co.jp/docs/news/2044189.html
