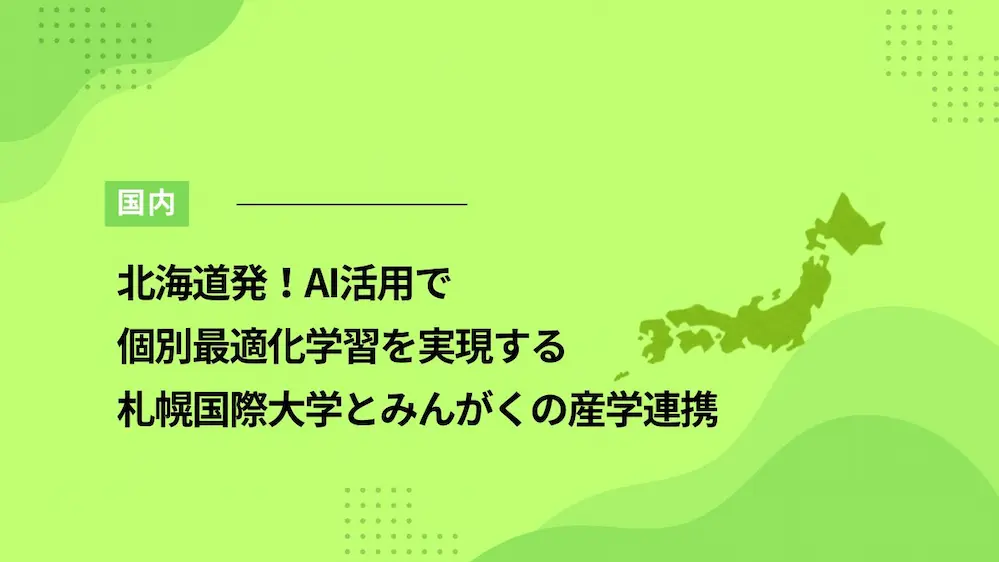
近年のChatGPTの登場で教育現場に衝撃が走って以来、生成AIをどう活用すべきかという議論が続いています。
しかし、ついに実践段階へと踏み出した取り組みが始まっています。
株式会社みんがくと札幌国際大学が包括連携協定を締結し、「スクールAI」を活用した次世代教育モデルの共創に乗り出したのです。
大人数授業でも一人ひとりに最適化された学習支援を提供し、AIリテラシー教育から教員の業務効率化まで、教育DXの全領域をカバーする壮大な実証研究。
果たして、この取り組みは学校教育の未来をどう変えるのでしょうか。
【記事の要約】
株式会社みんがく(東京都新宿区)は札幌国際大学(北海道札幌市)と包括連携協定を締結し、生成AIを活用した次世代教育モデルの共創を目指している。
本連携は2025年6月から開始され、4つの重点分野を中心とした取り組みを展開する。
第一に、同社が開発する「スクールAI」を活用した個別最適化学習支援環境の提供である。
大人数授業でもAIによる対話的かつ個別化された学習支援を可能にする。
第二は、AI時代に求められる倫理教育の共創で、AIリテラシーと学術的倫理の両面を指導する教育プログラムを開発する。
第三に、教員の業務効率化とAI活用スキル向上を支援し、レポート評価支援機能の導入や研修コンテンツの提供を行う。
最後に、半年間の実証研究を通じて教育効果を検証し、その成果を学会や論文で全国に発信する計画である。
朝倉一民教授は、生成AIが学生の思考に与える影響と適切な活用リテラシーの必要性を指摘している。
(出典元:2025年9月1日 PR TIMESより)
今後の学校教育への活用と将来性は?
この連携事例は、学校教育の未来に重要な示唆を与えているでしょう。
まず、個別最適化学習の実現可能性が大きく広がります。
従来は困難だった大人数授業における一人ひとりへの対応が、AIによって効率的に実現できるようになります。
特に注目すべきはAIリテラシー教育の体系化です。
生成AIを「正答」として盲信する問題に対し、適切な活用方法と学術的倫理を同時に教える教育プログラムは、小中高校教育でも必須となるでしょう。
また、AI利用ログの記録や不適切使用の検知システムは、教育現場での健全なAI活用を支える重要な基盤となります。
教員の働き方改革も大きな可能性を秘めています。
レポート評価支援機能などにより、教員は本来の教育活動により多くの時間を割けるようになるはずです。
同時に、AI活用研修により教員のスキル向上も促進されます。
将来的には、この実証研究の成果が全国の学校に展開され、文科省ガイドラインに準拠した安全で効果的なAI教育環境が標準化されることが期待されます。
詳細はこちらをご覧ください。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000144.000079497.html
