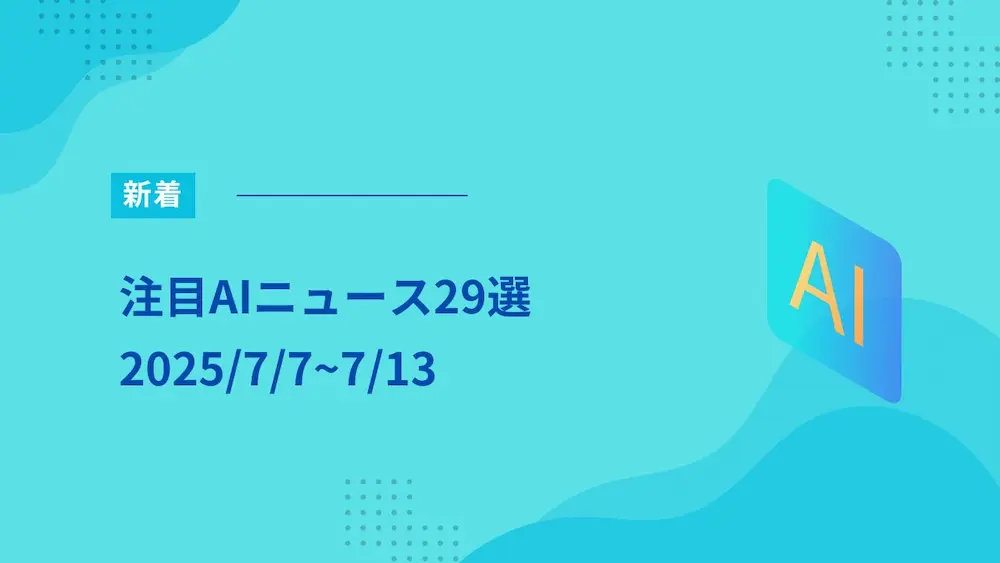
最新の生成AIニュース(2025年7月7日~7月13日)を、YouTubeチャンネル「いけともch_旧リモ研」の池田朋弘氏が注目した29のキーワードで紹介します。
1. PerplexityがAIエージェント搭載ブラウザのベータ版を発表
PerplexityがAIエージェント機能を統合したWebブラウザ「Comet」のベータ版を発表した。
月額200ドルのMaxプランユーザー限定で提供開始され、ChromiumベースでChrome拡張機能も利用可能である。右側のサイドパネルでAIアシスタントと対話でき、ブラウザ操作の自動化やタブ管理、メール要約などが可能だ。
2. ハイレベルな動画を誰でも簡単に生成可能
AI動画生成技術の進歩により、高品質な動画コンテンツの制作が大幅に簡素化された。
HeyGenなどのAI動画ジェネレーターでは、テキストや画像から数秒でプロ品質の動画を生成でき、リアルなAIアバターや多言語対応の音声クローニング機能を提供している。個人クリエイターから企業まで、専門的な編集スキル不要で動画制作が可能になった。
3. GeminiのサイドパネルGemが使用可能に
GoogleがGeminiのカスタムAI機能「Gem」をGoogle Workspaceアプリのサイドパネルからアクセスできるようにした。
Gmail、Googleドキュメント、スプレッドシート、スライド、ドライブで利用可能で、特定のタスクに特化したAIアシスタントを作成・活用できる。業務効率化とワークフロー最適化に大きく貢献する機能である。
4. Google Geminiに「Photo-to-Video」機能が追加
GoogleのGeminiに静止画から8秒間の動画を生成する「Photo-to-Video」機能が追加された。Veo 3動画モデルを活用し、アップロードした写真に動きや音声を追加できる。
Google AI ProとUltraサブスクライバー向けに順次展開され、720p解像度のMP4形式で出力される。すべての生成動画にはAI生成を示すウォーターマークが付与される。
5. Google DriveにGeminiでのファイル整理機能が追加
Google DriveにGeminiを活用した自然言語によるファイル管理機能が導入された。
サイドパネルから簡単な指示でファイルの移動、フォルダ作成、新規ドキュメント生成が可能になった。現在は一度に5ファイルまでの制限があるが、手動でのドラッグ&ドロップ作業を大幅に削減し、効率的なファイル管理を実現している。
6. ChatGPTの新機能「Study Together」試験導入
ChatGPTに教育支援に特化した新機能「Study Together」がテスト導入された。
従来の質問応答形式ではなく、AIが質問を投げかけてユーザーの思考を促進するソクラテス式問答法を採用している。単純な答えの提供ではなく、学習者の理解を深める対話型の教育体験を提供し、学習効果の向上を目指している。
7. xAIが「Grok 4」を発表
イーロン・マスクのxAIが新世代AIモデル「Grok 4」を発表した。Human Examsベンチマークで44%のスコアを記録し、従来モデルを大幅に上回る性能を示した。
月額300ドルの「SuperGrok Heavy」プランも新設され、より高度な処理能力を提供する。学術的質問においてPh.D.レベルを超える能力を持つとされている。
8. Dify v1.6.0リリース~MCP対応と操作性・安定性を強化
オープンソースのLLMアプリケーション開発プラットフォーム「Dify」がバージョン1.6.0をリリース。
Model Context Protocol(MCP)への対応により外部ツールとの連携が大幅に強化され、Claude DesktopやVS Code拡張機能との統合が可能になった。UIの改善と安定性向上により、開発者体験が大幅に向上している。
9. LM Studioが商用利用も完全無料化へ
ローカルLLM実行プラットフォーム「LM Studio」が商用利用を含めて完全無料化を発表した。
これまで月額29ドルだった商用ライセンスが不要となり、企業でも自由にローカルAIモデルを活用できるようになった。プライバシー重視の企業や個人開発者にとって、コスト負担なしでAI開発環境を構築できる画期的な変更である。
10. トヨタが首都圏で1000体の「人格AI」行動シミュレーション実施
トヨタ自動車が首都圏において1000体の人格AIを用いた大規模な行動シミュレーション実験を開始した。
各AIには異なる性格や行動パターンが設定され、交通流動や都市計画の最適化に向けたデータ収集を行っている。自動運転技術の向上と都市インフラの効率化を目的とした革新的な取り組みである。
11. シチズンマシナリーがAIで部品見積もり支援サービスを開始
シチズンマシナリーがAI技術を活用した部品見積もり支援サービスを正式に開始した。
過去の製造データと機械学習を組み合わせ、複雑な部品の加工コストを高精度で自動算出する。従来数時間かかっていた見積もり作業が数分に短縮され、製造業界の業務効率化と競争力向上に大きく貢献している。
12. HubspotがAI活用での3つの成果を発表
マーケティングプラットフォームのHubSpotがAI活用による3つの主要成果を発表した。
顧客対応の自動化により応答時間が70%短縮、リード品質の向上で成約率が25%増加、コンテンツ生成の効率化で制作時間が60%削減された。AI導入による具体的なROI向上事例として、多くの企業が参考にしている成功モデルである。
13. サイバーエージェントが生成AIを「全社インフラ」に
サイバーエージェントが生成AIを全社的なインフラとして本格導入することを発表した。
全従業員がAIツールにアクセス可能な環境を構築し、業務プロセスの標準化を進めている。広告制作、コンテンツ開発、データ分析など幅広い領域でAI活用を推進し、デジタル企業としての競争優位性を強化している。
14. 電通グループが約1000人規模のAI開発組織を発足
電通グループが約1000人規模の大型AI開発組織を新設した。
クリエイティブ制作からデータ分析、顧客体験設計まで、AI技術を活用した総合的なマーケティングソリューションの開発を目指している。広告業界におけるAI活用の先駆的な取り組みとして注目され、業界全体のデジタル変革を牽引する組織として期待されている。
15. SHIFTが「生成AI 360°」で社内AI活用を加速・定着へ
ソフトウェアテスト大手のSHIFTが「生成AI 360°」プログラムを開始した。
全社員を対象とした包括的なAI活用推進施策で、教育研修から実践導入まで段階的に展開している。テスト自動化、コード生成、ドキュメント作成など業務全般でAI活用を標準化し、生産性向上と品質向上の両立を目指している革新的な取り組みである。
16. MCPは手軽に自作可能へ簡素化
Model Context Protocol(MCP)の自作開発が従来より大幅に簡素化された。
開発者向けのSDKとドキュメントが充実し、数行のコードで外部ツールとAIモデルを連携できるようになった。GitHubやSlack、データベースなど様々なサービスとの統合が容易になり、カスタムAIアプリケーションの開発障壁が大幅に低下している。
17. ChatGPT EnterpriseとTeamプランに「クレジット制」導入
OpenAIがChatGPT EnterpriseとTeamプランにクレジット制課金システムを導入した。
従来の月額固定制から使用量に応じた柔軟な料金体系に変更され、企業の利用実態に合わせたコスト最適化が可能になった。大規模利用時の割引制度も設けられ、企業のAI導入コストを大幅に削減できる仕組みが整備された。
18. OpenAIがAI搭載ブラウザでChromeに本格挑戦へ
OpenAIがAI機能を統合した独自Webブラウザの開発を本格化させ、Google Chromeへの挑戦を開始。
ChatGPTとの深い統合により、検索、要約、翻訳、コンテンツ生成が seamlessに実行できる。プライバシー保護とAI支援のバランスを重視した設計で、ブラウザ市場の勢力図を大きく変える可能性がある革新的なプロダクトである。
19. OpenAIがオープンモデル公開を再度延期~安全性重視の徹底検証へ
OpenAIがオープンソースモデルの公開を再度延期し、安全性検証を徹底することを発表した。
AI安全性研究の進展と悪用防止対策の強化を優先し、段階的なリリース戦略を採用している。研究コミュニティからは批判もあるが、責任あるAI開発の姿勢として評価する声も多く、業界標準の確立に向けた重要な判断である。
20. AWSがAnthropicとAIエージェントのマーケットプレイス開設
AmazonがAnthropic社と共同でAIエージェント専用のマーケットプレイスを開設した。
企業向けに特化したAIエージェントの売買プラットフォームで、業務自動化、顧客対応、データ分析など用途別のエージェントが提供される。Claude技術をベースとした高品質なエージェントが中心で、企業のAI導入を大幅に加速させる基盤となっている。
21. AIに持続的記憶を与える「MemOS」を上海交通大などが開発
上海交通大学の研究チームがAIシステムに長期記憶機能を付与する「MemOS」を開発した。
従来のAIが持つコンテキスト制限を克服し、過去の対話や学習内容を永続的に保持できる革新的なシステムである。個人化されたAIアシスタントの実現に向けた重要な技術的ブレークスルーとして、学術界と産業界から高い注目を集めている。
22. 家庭内スマホ・PCを統合して自作AIクラスターを構築できる「exo」公開
オープンソースプロジェクト「exo」が家庭内の複数デバイスを統合してAIクラスターを構築するソリューションを公開した。
スマートフォン、PC、タブレットなどの処理能力を結合し、大規模言語モデルの分散実行を可能にする。個人でも高性能なAI環境を低コストで構築でき、プライバシーを保護しながら強力なAI機能を利用できる画期的なシステムである。
23. Hugging Faceが公開したオープンソースロボット発表
Hugging Faceがオープンソースのヒューマノイドロボット「Reachy Mini」を発表した。
身長60cmの小型ロボットで、AI研究者や開発者が手軽にロボティクス実験を行えるプラットフォームとして設計されている。3Dプリント可能な設計図とソフトウェアが公開され、教育機関や個人開発者でも本格的なロボットAI開発に取り組める環境が整備された。
24. OpenAIがジョニー・アイブのioを正式に買収、Windsurfの買収を中止
OpenAIが元Apple デザイナーのジョニー・アイブが設立したデザイン会社「io」を正式に買収した。一方で、AI開発ツールのWindsurfの買収計画は中止された。
ハードウェア製品開発への本格参入を示唆する戦略的な動きで、AIとデザインの融合による新たなプロダクト開発が期待されている。Apple的な洗練されたユーザー体験の実現を目指している。
25. 欧州出版社がGoogleのAI Overviewsに「独禁法違反」申し立て
欧州の主要出版社がGoogleのAI Overviews機能に対して独占禁止法違反の申し立てを行った。
検索結果でAIが生成した要約が表示されることで、オリジナルサイトへのトラフィックが大幅に減少し、出版社の収益に深刻な影響を与えているという。AI時代における情報流通とコンテンツ制作者の権利保護をめぐる重要な法的争点となっている。
26. 「ググるは崩壊する」HubSpot CEOが説くAI時代のマーケ戦略転換
HubSpot CEOが「ググる」という従来の検索行動が崩壊し、AI時代に適応したマーケティング戦略への転換が急務であると警告した。
AIアシスタントとの対話型検索が主流になることで、SEO中心の従来手法は効果を失うとしている。企業は対話型AIに最適化したコンテンツ戦略と顧客接点の再構築が必要であると提言している。
27. AI音声で米国務長官装う詐欺が発生
AI音声合成技術を悪用し、米国務長官になりすました詐欺事件が発生した。
高度な音声クローニング技術により、本人と区別がつかないレベルの偽音声が生成され、外交関係者を標的とした詐欺に使用された。AI技術の悪用による新たな犯罪形態として国際的な警戒が強まっており、音声認証システムの見直しと対策強化が急務となっている。
28. 情報通信白書の令和7年版~日本は他国に比べて大きくAI利用に遅れ
総務省が発表した令和7年版情報通信白書で、日本のAI利用率が主要国と比較して大幅に遅れていることが明らかになった。
企業のAI導入率は米国の半分以下で、特に中小企業での活用が進んでいない。デジタル人材不足と投資意欲の低さが主要因とされ、国際競争力維持のための抜本的な対策が求められている。
29. BCG「AI at Work 2025」~日本はAI関連で世界平均を下回る
ボストンコンサルティンググループの調査「AI at Work 2025」で、日本のAI活用とAIエージェント導入率が世界平均を大幅に下回ることが判明した。
特に業務自動化とAIエージェントの活用において、アジア太平洋地域内でも最下位レベルの結果となった。組織文化の変革と経営層のコミットメント不足が主要課題として指摘されている。
日本の教育分野におけるAI活用の可能性は?
AIニュースの中で、日本の教育現場で注目すべきはChatGPTの「Study Together」機能でしょう。
この機能は従来の質問応答形式とは異なり、AIが学習者に質問を投げかけて思考を促進するソクラテス式問答法を採用しています。
これにより、単純な答えの暗記ではなく、深い理解と批判的思考力の育成が期待できます。
また、Google Geminiの画像から動画生成機能も教育現場で大きな可能性を秘めています。
教師が静止画から8秒間の動画を簡単に作成できるため、視覚的で分かりやすい教材制作が可能になり、特に理科の実験や歴史の出来事を動的に表現することで、学習者の理解度向上に貢献するでしょう。
さらに、MCPの自作機能により、塾や学校が独自のAI学習支援ツールを開発できるようになります。
これは日本の教育機関がAI活用で遅れている現状を打破する重要な機会となり、個別最適化された学習環境の構築を可能にします。
これらの技術の組み合わせで、日本の教育現場におけるAI活用が飛躍的に進歩することが期待されます。
ぜひこの記事を参考に、今後の教育現場での生成AI活用を検討してみてください!
参考:
