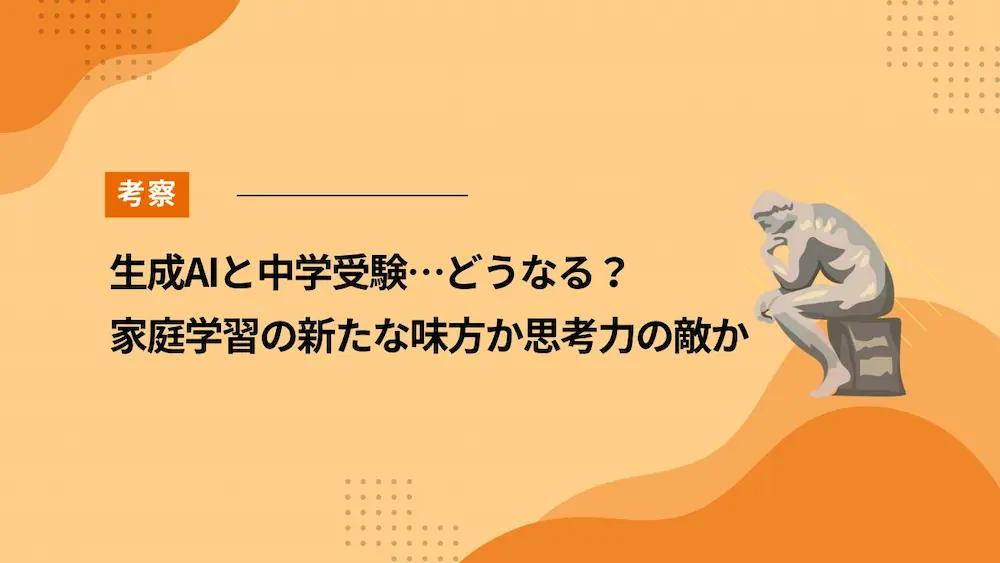
「ChatGPTで宿題やっちゃダメ?」
「AIに頼ると子どもの考える力が育たないのでは?」
―― 2022年の登場以来、教育現場を揺るがしてきた生成AI。
特に中学受験を控える家庭では、その活用法に頭を悩ませる保護者が増えています。
基礎問題の解説から個別化された学習プランの作成まで、生成AIは確かに強力な学習ツールとなり得ますが、その一方で思考力の平均化や依存のリスクも指摘されています。
そこで、教育専門家たちが語る「正しい生成AIとの向き合い方」と「これからの学校教育の可能性」を紹介しましょう。
【記事の要約】
生成AIは2022年のChatGPT登場以降、教育分野でも急速に普及している。
文部科学省は、2024年12月に小中高向けの生成AIガイドラインを発表し、2023年度からは「生成AIパイロット校」での実証も始まった。
一方で、大人たちの間では「積極的に使う人」と「まったく使わない人」の二極化が進み、保護者からは子どもの思考力低下を懸念する声も上がっている。
中学受験における生成AIの活用については、専門家は「基礎から標準レベルの問題解説には有効」と評価する。
ライフイズテック取締役の讃井氏は「生成AIは子どもに伴走する優秀な家庭教師になり得る」と述べ、プログラミング教育での成功体験創出に効果があると指摘する。
一方、プロ家庭教師の長谷川氏は「難関校レベルの複雑な問題はまだ解けない」と限界も示す。
また、生成AIを効果的に活用するには子どもの語彙力や基礎学力が前提となり、これがない状態では効果が薄いという。
生成AIの具体的な活用法としては、①わからない問題の解説、②類似問題の作成、③学習スケジュール管理などが挙げられる。
ただし、13歳未満の小学生が単独で使用するのは規約上難しく、親子での共同利用が基本となる。
専門家は「生成AIを使わせないという選択肢はない」と指摘し、適切な距離感を保ちながら活用する重要性を強調している。
特に「うまく活用できる家庭」と「そうでない家庭」の間で教育格差が生じる可能性も懸念されており、保護者自身が生成AIを理解し、子どもに適切な使い方を教えることが求められている。
(出典元:2025年5月5日 THE GOLD ONLINEとYahoo!ニュースの共同連携企画より)
学校教育への示唆と将来の可能性は?
生成AIは学校教育に新たな可能性をもたらしています。
小学校低学年では音楽作成や理科実験のアドバイザーとして活用されており、創造的な学びを促進する効果が期待できます。
今後の学校教育では、生成AIを「思考のパートナー」として位置づけることが重要です。
単に答えを出させるのではなく、アイデアの構成や文章改善のアドバイスを求めるなど、深い学びにつながる対話的な活用法を教えることで、子どもたちの俯瞰的思考力を育むことができます。
また、生成AIは個別最適化学習の強力なツールとなる可能性があります。
子どもの名前や好きなキャラクターを取り入れた問題作成など、個々の興味関心に合わせたコンテンツ生成が容易になります。
一方で、デジタル機器の長時間使用による身体感覚の希薄化や対人関係への影響も懸念されており、リアルな体験とのバランスを取ることが課題です。
将来的には、生成AIを活用した学習と従来の学習を組み合わせたハイブリッド型教育が主流になるでしょう。
そのためには、教師や保護者が生成AIの特性を理解し、適切な指導法を確立することが不可欠です。
生成AIの進化は非常に速く、半年も経てば大きく変わると言われている中、教育現場も常に最新動向を把握し、柔軟に対応していくことが求められています。
